
「ルッキズム」が引き起こす問題とは?解消に向けた動きについても解説
update: 2025.1.18
Contents
「ルッキズム」が引き起こす問題とは?解消に向けた動きについても解説
現代社会でますます問題視されている「ルッキズム」は、外見や身体的特徴で人を評価し、差別を助長する思想や行動を指します。「美しい」外見を持つ人々が社会的に優遇される一方、外見に対する偏見や先入観が引き起こす不平等も深刻化しています。
本記事では、ルッキズムの概念や歴史、現代社会における影響について解説するとともに、脱ルッキズムに向けた取り組みや個人ができる対策についてもご紹介します。
ルッキズムとは?
「ルッキズム」とは、英語の「look」(外見)と「-ism」(主義や思想)を組み合わせたもので、外見や身体的特徴で人を評価したり差別したりする思想や社会現象のことを指します。日本語では「外見至上主義」と訳されることが多いです。外見が美しいとされる人が優遇され、そうでない人が不利な扱いを受ける。ルッキズムという言葉は、外見が社会的な評価基準として重視されがちな現代社会において、近年注目を集めています。
ルッキズムの事例
ルッキズムは私たちの「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」の1つであり、他人の外見に対する偏見や先入観、それに伴う差別的な判断や行動は日常生活に潜んでいます。
具体的な事例を見てみましょう。
- 「身長が170㎝ない男性は恋愛対象外だ」
- 「女性はムダ毛がなくて当たり前だ」
- 「太っている人は自己管理ができていない・努力していない」
- 「あの人はイケメン・美人だから何でもできそう」
- 「西欧人の方が東洋人よりもかっこいい・きれい」
- 「自分はブスだから何もうまくいかない」
- 「Aさんみたいにかわいくなりたい」
これらの会話は、日常生活の中でも耳にすることがあるのではないでしょうか。私たちは、見た目の違いに優劣をつけたり、特定のイメージと結び付けたりして、他人や自分自身の容姿に対して日常的に外見至上主義的な判断をしているのです。
ルッキズムが生まれたのはいつから?
では、ルッキズムという概念はどのように生まれ、広まってきたのでしょうか。
ルッキズムの歴史
ルッキズムは、アメリカで公民権運動全盛期の1960年代に始まった、「ファット・アクセプタンス運動」の中で生まれた表現です。この運動は、肥満差別の廃絶を訴えるもので、「ルッキズム」という言葉は1978年にアメリカの雑誌「ワシントン・ポスト・マガジン」にて初めて使用されたといわれています。その後、肥満だけでなく、容姿や年齢、人種など様々な側面において、外見を理由とする差別をなくすための運動やメディアなどで広く使われるようになりました。
日本でのルッキズムの広まり
日本で「ルッキズム」という表現が使われるようになったのは、比較的最近のことです。しかし、昭和の時代には「容姿端麗」を条件として求人票に載せることが許容されていたことなどから、その考え方自体は古くから存在していたと言えます。
近年では、2021年に東京オリンピック・パラリンピックの開閉会式の企画・演出責任者が、女性タレントの容姿をブタに見立てて揶揄するという提案をしていたことが発覚し、その後辞任するというニュースが話題となり、ルッキズムが注目されました。その年の12月には、8年ぶりの全面改訂を行った三省堂国語辞典に「ルッキズム」が新語として追加され、2022年には新語・流行語大賞にもノミネートされています。
ルッキズムのSDGsとの関係
ルッキズムは、近年世界中で注目を集めているSDGsとも関係しており、特に10番目の目標「人や国の不平等をなくそう」の達成において克服すべき重大な課題となっています。外見による差別は、年齢、性別、国籍、人種や身体的特徴に基づく不平等を助長します。これらのあらゆる差別をなくすことが、SDGsの目標達成のために不可欠です。

ルッキズムを加速させる原因
近年、問題視する動きが高まっているルッキズム。ここからは、ルッキズムを加速させている要因についてみていきましょう。
メディアやインターネットの影響
テレビや雑誌では、顔やスタイルの美しい女優やモデルが起用されることが多く、視覚的な美が強調されます。そして、特定の外見を理想とする美の基準が作り上げられることで、その基準に該当しない人を「劣っている」とみなす偏見が生まれています。このように、見た目の商業化は、ルッキズムを高めている要因の1つとなっています。
また、総務省が公開している資料(※1)では、「メタバース(インターネット上の仮想空間)で用いられるアバターは美少女であることが多く、それがルッキズムを助長する側面もあるのではないか」と言及されています。
出典:(※1)「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」中間とりまとめ | 総務省
SNSの普及
SNSの普及により、私たちは毎日のようにインフルエンサーやアイドル、モデルなどの「美しい」見た目をしている人々を画面上で見ることができます。有名人だけではなく、友人や同年代の人たちが投稿した写真や動画によって、簡単に他人と比較することが可能になりました。加工技術の進歩により、本来の写真や動画を修正し、誰もが簡単に理想的なルックスを作り上げることができるようになった一方、SNS上での外見への誹謗中傷もエスカレートしています。
SNSは「いいね」機能やフォロワー数などによって評価が可視化されるため、他者との比較を促進します。人々は、「いいね」やフォロワー数を稼ぐために、メイクアップや加工技術なども用いてさらなる「美しさ」を追求するようになるのです。
エステや脱毛、美容整形などの広告やインフルエンサーによるPRが増えたことで、いわゆる「美容課金」への心理的ハードルが低くなったこともルッキズムの加速に拍車をかけています。
2023年にプラン・ユースグループが行った調査(※2)によると、「自分の容姿について悩んだことはありますか?」という質問に対し、約9割の若者が「いつも悩んでいる・悩んだことがある」と回答しています。また、自分の容姿に関心を持ったきっかけ(複数回答)として「SNS」と回答した人は51.5%であり、40.3%の「雑誌、テレビなどのメディア」よりも多い結果となりました。
出典:(※2)ルッキズム(外見至上主義)を考える「ユースを対象にした容姿に対する意識調査」報告書 | プラン・ユースグループ
見た目が「良い」と得をする社会
ルッキズムは、私たちのアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)により形成され、社会に根付いています。
その代表例として挙げられるのが、企業の「顔採用」です。人材採用などの場面において、外見についても評価の対象としたり、採用担当者が履歴書の写真などを見て無意識に容姿を加点対象としたりするなど、容姿端麗な人がキャリア形成や経済的自由度において有利になることがあるのです。
このような、社会全体に蔓延している外見至上主義の価値観が、ルッキズムを加速させています。
ルッキズムが引き起こす問題
現代社会でルッキズムが広がっている原因についてみてきましたが、ここからはルッキズムがもたらす問題についてご説明します。
差別や不平等の助長
特定の見た目を美しいとみなすルッキズムは、様々な差別を助長します。例えば、肌の色や体格、目鼻の形など、特定の人種が持つ身体的特徴が他の人種よりも優れている(劣っている)という見方は人種差別につながります。また、頭髪の量や顔のしわなどで年齢を断定するといった行為は、年齢差別と言えます。メディアなどが特定の外見による美の基準を強調することで、こうした外見による差別が社会に浸透し、個人の自尊心の低下や経済的・社会的格差の助長につながります。
また、ルッキズムの影響により、整形手術を行う人も増えています。例えば、「男らしさ・女らしさ」を追求し、豊胸手術をする女性や、逆に胸を小さくする男性。最近の日本では、大きな目を手に入れるために二重整形をする人が多く、ある病院での二重手術を行った10代の患者件数は、2015年から2020年にかけて38.5倍に増えています(※3)。美容整形自体が問題というわけではありません。しかし、「外見を変えたい」という思いは、ルッキズムが引き起こす差別や偏見からくるものである場合が多いと想像できます。美容整形に限らず、化粧や服の着こなしなど、私たちの普段の行動は、ルッキズムに基づくものが多いのではないでしょうか。
また、先に述べた「顔採用」などは、能力などの見た目以外の部分が正当に評価されないことを意味します。このように、見た目による待遇の差が、就職・昇進・教育などの場面において不平等を引き起こしています。
出典:(※3)未成年の「美容整形」に関するアンケート調査 | 東京イセアクリニック
精神的・身体的不調の増加
ルッキズムは、精神的・身体的不調を引き起こすことも問題視されています。
自尊心の低下
ルッキズムは個人の多様性を否定し、不安や自信の喪失を引き起こします。こども家庭庁が出した「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」(※4)によると、日本の若者の自尊感情は他国と比較して低いとされています。また、同調査において、自分の容姿について「心配」である、又は、「どちらかといえば心配」であると答えた人は、合わせて54%でした。アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデンにおいても、約50%を占めています。このことから、世界各地で半数近くの若者が自分の容姿にネガティブな感情を抱いていることが分かります。このようなルッキズムによる自己受容感の低下は、うつ病や不安障害のリスクを増大させます。
出典:(※4)我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査 | こども家庭庁
摂食障害
ルッキズムは摂食障害を引き起こすこともあります。過度なダイエットや外見へのプレッシャーが精神的な問題を引き起こし、食べることに恐怖を感じたり、いったん飲み込んだものを吐き出してしまったり、自分でコントロールできずに食べ過ぎてしまったりといった症状を引き起こします。摂食障害は治療に時間と労力がかかり、うつ病や不安障害などの他の精神疾患を併発することもあります。
醜形(しゅうけい)恐怖症
続いて、醜形恐怖症についてです。醜形依存症は、実際には存在しない外見上の欠点を過剰に気にしてしまい、1日に何度も鏡を確認したり、人目につかないように外出を拒むなど、日常生活に支障をきたす精神疾患です。美容整形を身体の一部が不自然な形になるまで繰り返してしまうこともあります。
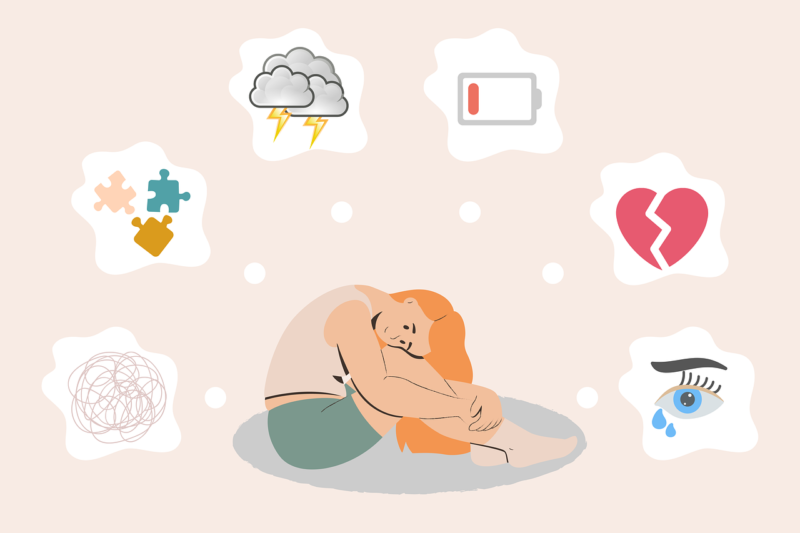
脱ルッキズムに向けた取り組み
ここからは、ルッキズムが引き起こす問題の解消に向けた取組についてご紹介します。
プラスサイズモデル
これまでのファッションモデルのイメージを覆し、平均体重以上のモデルである「プラスサイズモデル」が活躍し始めています。これまで、広告などに起用されるモデルのイメージが美の基準として定着し、多くの人々を苦しめてきました。そういった状況を踏まえ、従来の美の基準にとらわれない、身体的な多様性を尊重したモデルを起用する動きが、企業やブランドの間で広まっています。
また、障がいを持つ人もモデルとして活躍するようになっています。
ミスコン・ミスターコンの廃止・見直し
外見で優劣を競うミスコン・ミスターコンの廃止、また、審査基準などの見直しも行われています。上智大学では、従来の「ミス・ミスターソフィアコンテスト」を2020年に廃止し、社会を先導し活躍する人材の輩出を目指す「ソフィアンズコンテスト」を新設しました。このコンテストは、男女を問わず参加でき、「自身の魅力や取り組みを効果的に伝えるインフルエンサーとしての活動」を競うものとなっています(※5)。また、100年以上の歴史を持つアメリカの「ミス・アメリカ」でも、2019年に水着審査が廃止され、初めて黒人女性が選ばれるなど、審査方法に変化がみられます。このように、男女の区別が廃止される、発信力などの外見以外による評価システムが導入されるなど、これまでの評価基準が見直されています。
出典:(※5)Sophian’s Contest | 上智大学
お笑い芸人の容姿いじりネタの見直し
ルッキズムへの批判が高まる中で、笑いを届ける側と受け取る側、双方の意識の変化により、お笑いにおける見た目のいじりや自虐ネタも見直されつつあります。最近では一昔前に比べ、お笑い芸人が自分や相方の見た目を卑下することで笑いをとるようなネタは減っているように感じます。
採用基準の見直し
先に挙げた「顔採用」などの不公平な採用基準も見直されつつあります。アメリカでは通常、履歴書に年齢や顔写真を載せる必要がありません。日本でも、見た目による就職差別に対抗する動きとして、2020年に日本アルビズムネットワークが行った「履歴書から写真欄もなくそう」キャンペーンでは、12000人以上の署名が集まっています(※6)。このように、外見や性別、年齢、人種などによらない、才能や人柄が適切に評価される公正な選考を実現する動きが高まっています。
出典:(※6)履歴書から写真欄もなくそう | change.org
ノルウェーの事例
ノルウェーでは、特定のボディイメージが広まりやすいものに関する広告について、厳しく規制されています。例えば、12歳未満の子どもに対するテレビ広告、つまり、おもちゃなどの子ども向け製品の広告は禁止されています。子ども向けのおもちゃに関して、「男の子は青」「女の子はピンク」といったステレオタイプに基づく商品はほとんどありません。化粧品に関する広告にも、特定のボディイメージが人々の心身に及ぼす影響を鑑み、規制が行われています。また、企業などが編集・加工した写真を使用する際には、その写真が加工されていることを開示する義務が法律によって課されています。
ルッキズムの高まりに対して個人ができる取り組み
続いて、ルッキズムの高まりに対して私たち個人ができる取り組みについてご紹介します。
SNSとの付き合い方
近年、特に若い世代を中心に普及しているSNS。連絡ツールや情報収集の手段にもなっているため、ついSNSに投稿されている動画や画像を見入ってしまうことも少なくないのではないでしょうか。そこには、インフルエンサーやアイドルの動画など、「魅力的な」外見を持つ人々に関する情報が溢れています。加工技術を用いてより「魅力的」に見せようとしているものもありますが、それらを本物であると思い込み、自分自身と比較し、落ち込んだり精神的に病んだりしてしまうこともあります。SNSに溢れる情報に翻弄されないためにも、「SNS上の投稿はあくまでもその人の広告である」と割り切り、1日の使用時間を制限するなど、SNSとの適切な距離を保つことが大切です。
アサーティブコミュニケーション
アサーティブコミュニケーションとは、相手の立場や意見を尊重しつつ、自分の気持ちを大切にした自己表現を行うスキルです。自分も相手も尊重することで、状況を客観的に捉えられるようになり、円滑な人間関係を築くことができます。アサーティブコミュニケーションを身に着けることは、近年、ルッキズム解消につながる方法の1つとしても注目されています。

ルッキズムのまとめ
「ルッキズム」とは、外見や身体的特徴を基準に人を評価する社会的な偏見や差別を指し、SNSが普及する現代社会において深刻な問題となっています。外見に基づく差別が個人や社会に及ぼす悪影響が懸念される一方で、ルッキズムを解消する取り組みも進んでいます。プラスサイズモデルの起用やミスコンの見直しなど、外見にとらわれない多様性を尊重する動きが広がっているとともに、SNSの使用の見直しやアサーティブコミュニケーションなど、脱ルッキズムに向けて個人でできる取り組みも注目されています。社会全体でルッキズムを克服し、外見以外の価値が尊重される環境を作ることが、より平等で多様性を重んじる社会の実現に向けて重要です。
update: 2025.1.18




