
相対的貧困とは?日本など先進国でも深刻な貧困問題をわかりやすく解説
update: 2025.1.11
Contents
相対的貧困とは?日本など先進国でも深刻な貧困問題をわかりやすく解説
これまで「貧困問題」といえば、特に途上国などの貧困地域で暮らす、日々の食事や生活もままならない人々の貧困が注目されてきました。
しかし近年、日本を含む多くの先進国で、「相対的貧困」という別の種類の貧困に苦しんでいる人々が多くいることが問題視されているのです。
その上でこの記事では、そもそも「相対的貧困」とは何なのか、日本などの先進国で実際にどんな問題が起きているのかなどについて、わかりやすく解説しています。
最後には、相対的貧困の解決に向けた取り組みもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
そもそも相対的貧困とは?

相対的貧困の定義
まず、相対的貧困の定義を説明します。
相対的貧困とは、簡単に言うと、その国や地域に住む多くの人々に比べて所得が少ない状態のことを指します。
具体的には、それぞれの国や地域における、等価可処分所得の中央値の半分を基準として、そのラインを下回っている状態が、相対的貧困と呼ばれます*。
*参照:厚生労働省:国民生活基礎調査(貧困率) よくあるご質問
絶対的貧困との違い
相対的貧困とよく区別されるのが、「絶対的貧困」です。
絶対的貧困は、一般的に、衣食住などの必要最低限の生活もままならないような貧困状態を指し、主に途上国などで深刻な問題です。具体的には、世界銀行は一日2.15米ドルでの生活を基準として、それを下回る金額で生活している状態を絶対的貧困と定義しています*。
一方で相対的貧困は、そのような一定の基準は設けず、あくまでその人がその国や地域の他の人々と比べて貧困なのかどうかということが基準となります。
そのため、相対的貧困がどの程度の貧困状態なのかは、その国や地域全体の豊かさの程度によって大きく変わるのです。
*参照:日本ユニセフ協会:1. 貧困をなくそう|SDGsクラブ- 日本ユニセフ協会
先進国における相対的貧困の現状

ここまでの説明を見ると、なんとなく、相対的貧困は絶対的貧困ほど深刻な問題ではないのではないか?と思われるかもしれません。
特に、国や地域自体が豊かな先進国なら、たとえその中で相対的な貧困があったとしてもそもそも最低限の生活すらできない途上国の絶対的貧困に比べればそれほど深刻ではないように思われるかもしれません。
しかし実は、その見方は必ずしも適切ではありません。
実際に先進国の相対的貧困は、場合によっては途上国の絶対的貧困の問題と同じか、あるいはそれ以上に厄介な問題を引き起こすことがあるのです。
相対的貧困が引き起こす社会問題とは?
●健康面でのリスク
まず、相対的貧困に苦しむ人々は健康面でのリスクを抱えています。たとえ先進国の中で、かろうじて標準的な生活ができていたとしても、そのような日々の生活の出費に圧迫されて、結果的に病院に行くためのお金がなくなったり、栄養バランスの取れた食事をする余裕がなくなったりして、健康状態の悪化を招いてしまいます。
●教育格差
貧困によって教育格差が生まれるのは、決して途上国だけの問題ではありません。実際に先進国では、途上国のようにそもそも「学校に通えない」という状況はそれほど多くありませんが、代わりに、学校以外での塾や家庭教師などの教育機会にアクセスできなかったり、中学校までは学校に通えても、高校、大学に通うのは金銭的に難しいといったケースが多くあります。
※特に、日本のように偏差値が将来の収入に影響する「学歴社会」の国では、そのような教育格差が子どもの将来の収入の格差にもつながり、いわゆる「貧困の連鎖」を生み出す大きな要因になります。
●子どもの貧困、親による虐待
相対的貧困層の家庭では、特に子どもの貧困も深刻です。上記のような、健康面でのリスクや教育格差の問題に加え、特にその家庭における子どもは、親の精神的ストレスや日々の逼迫した生活環境などが影響して、親からの虐待を受けるリスクが高まると言われています。
日本における相対的貧困の現状

意外に思われるかもしれませんが、実は、日本は特に相対的貧困が深刻な国の一つです。
厚生労働省によると、2021年時点で日本の相対的貧困率は15.4%で、およそ7世帯のうち1世帯が相対的貧困の状態にある*ことがわかりました。
また、経済協力開発機構(OECD)が公表した他の国々のデータと比較すると、その日本の相対的貧困率が先進国の中で最悪の数値だったこともわかっています。
日本では特に、母子家庭など、ひとり親世帯の貧困が深刻で、2021年時点では全体の数値が15.4%だったのに対し、ひとり親世帯の相対的貧困率は44.5%にものぼりました*。
*参照:厚生労働省:各種世帯の所得等の状況
相対的貧困は、“見えづらい”
このように、日本の相対的貧困が実は非常に深刻で、特に先進国の中では最悪の貧困率だなどと言われても、中にはあまりピンと来ない方もいるかもしれません。
その原因の一つは、相対的貧困の“見えづらさ”にあります。
先進国における相対的貧困層の多くは、途上国の絶対的貧困のように、生きるために必要最低限の生活もままならない状況というわけではありません。むしろ最低限の食料のほか、一般的な住居や車、携帯電話なども持っている場合は多くあります。要するに、一見すると「普通」の生活をしているのです。
だからこそ、相対的貧困は認知されづらい問題だと言われています。しかしその認知されづらい状況の中で、周りの人々がふだん当たり前に得ている商品やサービスを得られずに苦しんでいる人々が多く存在している現状があるのです。
相対的貧困の解決に向けた取り組みとは?

日本では、相対的貧困の問題を解決するために国や自治体、企業、NPOなどさまざまなセクターが取り組みを行っています。
①生活支援
まず、相対的貧困層への生活支援として、国などによるひとり親世帯や生活困窮者への経済的な支援や、自治体、NPOなどによる相談支援などがあります。また、貧困家庭の子どもの栄養面をサポートするため、子ども食堂やフードバンクなどの取り組みも全国各地で行われています。
②就労支援
職がないために貧困に陥る人々も少なくありません。そこで、国は就労支援を積極的に行っており、求職者への相談支援や企業の紹介、職業訓練など、幅広いサポートを行っています。また、職業訓練や企業への人材紹介などの支援を専門に行っている企業やNPOもあります。
③子どもの学習支援・相談支援
教育格差と、その影響による「貧困の連鎖」を止めるためには、貧困家庭の子どもへの学習支援が重要です。実際、国やNPOによる無償の学習機会の提供や、企業による貧困家庭の子ども向けの教育事業などがあります。
また、学習支援だけでなく子どものための相談支援も大切です。特に、外からは“見えづらい”相対的貧困の家庭の中で、虐待などに苦しむ子どもたちを見つけ、助け出すきっかけになります。具体的には、自治体やNPOなどによる電話相談や、学校などでのカウンセリングの支援などが行われています。
まとめ|私たちにできることを考えよう
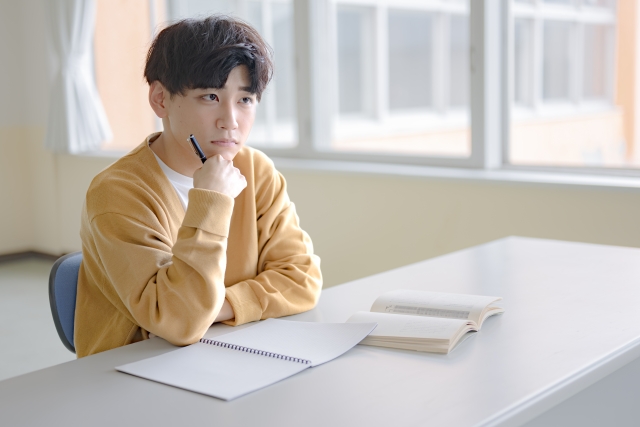
このように、相対的貧困とは、国や地域の中の多くの人に比べて所得が少ない状態のことで、実際に日本を含む多くの先進国で深刻な問題となっています。
特に、相対的貧困は人々の健康状態の悪化や、教育格差、子どもの貧困、虐待などの社会問題を引き起こすリスクを持っており、また相対的貧困は外からは“見えづらい”ため、解決が困難になっています。
一方で、その相対的貧困を解決するために、日本では国や自治体、企業、NPOなどによって生活支援、就労支援、子どもの学習支援・相談支援などの取り組みが行われています。
もしこの記事を読んでくださった皆さんの中に、相対的貧困の問題に関心を持っている方がいたら、ぜひ、自分が今、あるいは将来に、この問題の解決のためにできることを考えてみてください。そのためにはまず、この問題の具体的な現状や、原因、実際に行われている取り組みなどについて、深く知ることが不可欠です。
update: 2025.1.11




