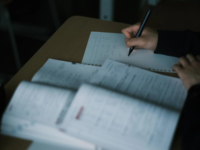世界の教育問題の現状は?子どもが学校に通えない理由や取り組み事例を徹底解説
update: 2024.12.17
Contents
世界の教育問題の現状は?子どもが学校に通えない理由や取り組み事例を徹底解説
現在、世界全体で学校に通っていない子どもの数は合計約2億4,400万人にのぼります(2021年時点)*。教育問題は、依然として世界で深刻な課題です。
しかし、一言に教育問題といっても、その具体的な課題や背景にある原因は、地域によって様々です。この記事では、世界全体の教育問題の現状を幅広く解説し、最後には具体的な解決策と、実際の取り組み事例をご紹介します。
いまこの記事を読んでくださっている皆さんが、これから何らかの形で教育問題に取り組んだり、教育問題の解決策を考えたりする上での参考になれば幸いです。
(*出典:UNESCO: New estimation confirms out-of-school population is growing in sub-Saharan Africa)
世界の教育問題の現状とは

現在、学校に通っていない子ども(6〜17歳)は世界全体で合計約2億4,400万います。
特に、それぞれの学齢期で学校に行っていない子どもの数は以下の通りです。
・小学校学齢期(6~11歳)=6,700万人(11人に1人)
・中学校学齢期(12~14歳)=5,700万人(7人に1人)
・高等学校学齢期(15~17歳)=1億2,100万人(3人に1人)
初等教育(小学校)から中等教育(中学校、高等学校)になるにつれて学校に行けない子どもが増えていることがわかります。特に、日本で高校に通っている年齢(15〜17歳)の子どもたちは、世界でおよそ3人に1人が学校に通うことができていません。
(出典:*UNESCO: New estimation confirms out-of-school population is growing in sub-Saharan Africa)
教育問題が深刻な地域(途上国の教育問題)
学校に通っていない子どもが多い地域は、やはり開発途上国に集中しています。中でも、サブサハラアフリカ地域(北アフリカを除いたアフリカ大陸サハラ以南の地域)と、南アジア地域(インド、パキスタン、バングラデシュなど)の国々では、特に多くの子どもたちが学校に通うことができていません。
特にサブサハラアフリカ地域では、学校教育を受けられない子どもの割合がいまだ増加傾向にあります。特に小学校に通っていない子どもの割合が高い国々は以下の通りです。
(南スーダン(62%)、赤道ギニア(55%)、エリトリア(47%)、マリ(41%)など)。
さらに途上国では、子どもたちが学校に通えない問題に加えて、そもそも教育の質が低いことや、中退率が高いことなども問題です。結果として、上記地域の途上国では識字率が低く、また計算ができない人々が多くいます。
※学校に通えない子どもの数が多い上位10カ国:インド、パキスタン、ナイジェリア、エチオピア、中国、インドネシア、タンザニア、バングラデシュ、コンゴ民主共和国、スーダン(2021年時点)。
(出典:*UNESCO: New estimation confirms out-of-school population is growing in sub-Saharan Africa)
女の子が学校に行けない問題
開発途上国では、ジェンダー格差による女子教育の問題も深刻です。2018年のUNESCOの報告によると、世界全体で約1億3,200万人の女の子が学校に通っていません*。
特に、上述したサブサハラアフリカ地域の、ニジェールやマリ、チャドといった多くの国々では、学校に行く代わりに家庭内での家事労働をさせられたり、早すぎる結婚(児童婚)や妊娠によって教育の機会を奪われる女性も多くいます。
また、パキスタンやアフガニスタンといった南アジア地域では、そもそも女性が教育を受ける必要性を認めない文化・宗教的価値観によって、女性の教育へのアクセスが制限されています。
そして特に途上国では、女の子が教育を受けやすい環境が整っていないことも大きな課題です。学校に女性教員が少ないことや、家から学校までの道のりが危険なこと、学校に男女別のトイレがなく月経中の女の子が学校に行きづらいことなど、女の子が学校で教育を受ける上での大きな障壁となっています。
(*出典:UNESCO: One in Five Children, Adolescents and Youth is Out of School)
日本における教育問題
教育問題は決して途上国だけの問題ではありません。日本は他の国々に比べて就学率は高いですが、一方で家庭の貧困・地域による教育格差など、深刻な課題も抱えています。
実際に、貧困家庭のこどもが学校以外での教育の機会(塾や習い事など)を得られなかったり、学費が払えないために高校を中退したり、大学に進学できないケースも少なくありません。また地域によっても、教育資源の偏りや、教師の質、進学率の差など、教育における格差があることは否めません。
加えて、不登校やいじめ、引きこもりといった問題も、日本では特に深刻な教育問題の一つです。
日本の教育問題についての詳しい内容は別の記事でもまとめています。気になる方は下記のリンクからご覧ください。
SDGs目標4の日本の現状|日本の教育問題や取り組み事例を解説
なぜ子どもたちは学校に通えないのか~4つの原因~

しかし、そもそもなぜ途上国の子どもたちは学校に通えないのでしょうか。この章では、その主な4つの原因を解説します。
①貧困による影響
必要最低限の生活もままならない途上国の貧困家庭では、子どもの教育が後回しにされている現状があります。特にそのような家庭では、子どもが遠くにある井戸まで水汲みに行ったり、外で働く親の代わりに家で幼い兄弟の世話をしたりするなど、家族のために家事や労働に従事しなければならず、そのため学校に行けなくなってしまうのです。
そして教育を受けられないまま大人になることで、収入の安定した職に就けず再び貧困に陥り、その子どももまた教育を受けられないという、いわゆる貧困の連鎖が、途上国の教育問題解決を妨げている原因となっています。
②教育のための環境が整っていない
途上国において教育のための環境が整っていないことも、子どもたちが学校に通えない原因の一つです。そもそも教師や学校の数が不足しいているために、農村部や僻地に住む子どもたちが近くで通える学校が無かったり、遠くにある学校まで行くための交通費の負担や、子ども一人で長距離を通学する危険性のために学校に通えないケースもあります。
さらに先述の通り、学校に男女別のトイレがないことで女の子が学校に行きづらいという課題もあります。
③戦争・紛争の影響
戦争や紛争の影響で学校が閉鎖されたり、避難所や軍の拠点としても使われる学校が攻撃の対象となって破壊されることもあります。また紛争地域では当然、子どもは安全に通学することができません。
さらに、いまだ多くの地域で紛争が続くアフリカでは、紛争の被害によって難民になったり、「子ども兵士」として戦闘に駆り出されたりして教育の機会を奪われてしまう子どもも決して少なくありません。
④文化・宗教の影響
地域の文化・宗教の影響で、子どもが学校に行けないケースもあります。実際、文化として教育の重要性が認知されていない地域では、やはり子どもを学校に行かせようとする親は少なくなってしまいます。
さらに、女の子より男の子の教育を優先させる慣習や、女の子の児童婚の文化、宗教に基づいた女子教育を否定する考え方なども、サハラ以南のアフリカや南アジアの途上国で、女の子が学校に通えない大きな原因になっています。
教育問題の解決策/ 具体的な取り組み事例

ここまで、世界の教育問題の現状と子どもたちが学校に行けないさまざまな理由を説明しました。
最後に、それらの教育問題に対する解決策を実際の取り組み事例とともに詳しくご紹介します。
解決策は、大きく分けて以下の3つの方向性があります。
・教育へのアクセスを増やす
・教育を受けやすい環境を作る
・教育の質を高める
それではひとつずつ具体的に解説していきます。
教育へのアクセスを増やす
まずは、途上国の子どもたちの教育へのアクセスを増やす取り組みです。
中でも特に多くのNGOによって行われている取り組みは、学校の建設・運営です。学校の数自体を増やすことで、農村部や僻地に住む子どもたちもより学校に行きやすくなります。また、オンライン教育を活用することで、同様に遠隔地の子どもたちに教育を届ける取り組みも行われています。
さらに、教科書・学用品の提供や、奨学金の支給を通して、貧困家庭の子どもたちがより教育にアクセスできるようにする活動も行われています。
実際に、2003年にブラジル政府が行った「ボルサ・ファミリア」プログラムでは、経済的に困窮する家庭に財政支援を行い、低所得層の子どもたちの教育機会を増やすと同時に、全体の就学率の向上にも寄与しました。
教育を受けやすい環境を作る
学校に通える子どもを増やすためには、「教育を受けやすい環境」を作ることも重要です。
実際に、教育問題に取り組む国連機関UNICEF(ユニセフ)や、その他NGOなどの団体は、具体的に以下のような活動を通して子どもたちが学校に行きやすい環境を整えています。
・学校周辺の交通手段の整備
→子どもが安全に学校に通えるようにする。
・学校での給食の配布
→栄養を摂ることで子どもの学習への姿勢を向上させる。また親にとって子どもを学校に通わせる理由になる。
・学校内の給水タンクの設置
→子どもが遠くの井戸や川まで水汲みに行って学校を休まなくていいようにする。
・学校内の男女別のトイレの設置
→月経中の女の子でも学校に通えるようにする。
・教育の重要性についての啓発活動
→親の教育に対する優先度を上げる。
教育の質を高める
学校教育へのアクセスができても、その教育の質が低ければ、結局収入が安定した職に就けず貧困に陥ってしまう可能性があります。
そのため、教員へのトレーニングや、効果的な教育カリキュラムの開発、さらに子ども一人ひとりに合わせた教育プログラムの提供など、教育の質を高めるための様々な取り組みが求められているのです。
中でも、特に子ども一人ひとりに合わせた教育を提供する取り組みでは、デジタルツールやAI技術を駆使した取り組みも多く行われています。
実際、日本の企業、株式会社すららネットが提供する独自のICT教材『すらら』は、インドネシアやスリランカ、フィリピン、エジプトなどの国々でも導入され、生徒一人ひとりに「個別最適化」した教育を提供しています。
国内・海外の教育問題に取り組む日本企業、企業の取り組み事例は下記の記事でまとめています。
教育問題のまとめ | 解決のために私たちにできること

このように、世界にはいまだ多くの教育問題があり、地域によってさまざまな理由で学校に通えていない子どもたちがいます。
そして国連や政府、NGO、企業といった各セクターが、その教育問題解決のためにさまざまな取り組みを行っています。
ではその中で、私たちにできることはなんでしょうか。
一つは、教育問題解決に直接取り組む団体に寄付を行ったり、活動にボランティアとして参加したりして、その団体の課題解決に貢献することです。
寄付やボランティアと聞くと一見小さな取り組みに思われますが、自分が特に解決したい課題に取り組んでいる団体を選ぶことで、間接的に自分の理想に近い社会課題解決を行うことができます。
update: 2024.12.17