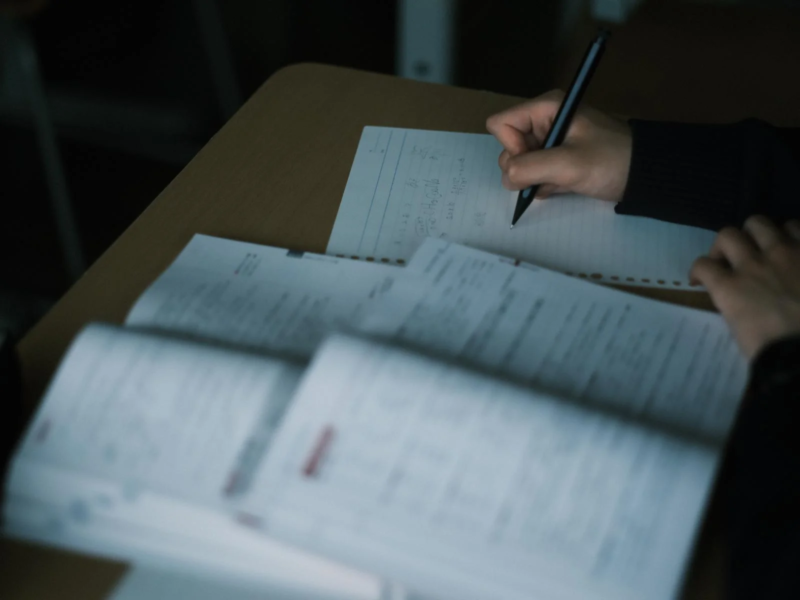
SDGs目標4の日本の現状|日本の教育問題や取り組み事例を解説
update: 2024.12.17
Contents
SDGs目標4の日本の現状|日本の教育問題や取り組み事例を解説
教育問題は決して途上国だけの問題ではなく、日本でも非常に深刻な問題だと、近年よく言われるようになりました。しかしそれでも、日本の教育問題はその深刻さの割に、未だ途上国の問題ほど注目されていません。
実際、「教育問題」や「SDGs目標4(質の高い教育をみんなに)」について調べようと検索しても、途上国についての記事はよく見つかる一方で、日本の教育問題について詳しくまとめられた記事はあまりありません。
そのためこの記事では、特に日本の教育問題に関心がある方に向けて、SDGs目標4の日本の達成状況や、教育問題の現状、取り組み事例など、日本の教育問題について幅広く、また詳しく解説しました。
もし上記のうち一つでもご関心のある内容があれば、この記事をご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。
SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」とは

そもそもSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」とはどのような目標なのでしょうか。
持続可能な世界を実現するための17の開発目標、SDGsの中で、目標4「質の高い教育をみんなに」は、文字通り教育分野で世界が達成するべき目標を掲げています。
目標の細かい内容は以下の10個のターゲット(目標をより細分化・具体化したもの)を見るとわかりやすいですが、全体的に重要な点は、
すべての人々が公平に、かつ質の高い教育を受けられるようにすること、です。
この目標に基づいて、実際に世界では学校に行けない子どもたちに教育機会を与えたり、質の高い教育を提供するための教育環境を整えたりするなど、さまざまな取り組みが行われています。
SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」のターゲット
4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。
4.2 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。
4.3 2030年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。
4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。
4.5 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。
4.6 2030年までに、全ての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。
4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。
4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。
4.b 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、並びにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。
4.c 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。
日本におけるSDGs目標4の達成状況

途上国など海外に比べると、日本のSDGs目標4の達成状況は全体的に良いと言えます。
実際、2023年に発表されたSDGsの達成度・進捗状況に関する国際レポート*では、日本のSDGs目標4の状況は「2030年までの目標達成に向けて順調な割合でスコアが増加している/目標達成値を超えている」と評価されました。

参考:SDSN: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/japan
特に、日本は就学率が高く、義務教育の制度もありほとんどの子どもたちが初等教育、中等教育を受けることができています。
さらに長年問題視されてきた学力の低下も、最近では一転して向上の兆しが見えています。2022年に行われた国際学力調査「PISA」では、「読解力」、「数学的リテラシー」、「科学的リテラシー」の3つの分野で日本の順位が上昇し、いづれも世界トップレベルとなっています。
このように日本の教育は、海外と比べて全体的に良い状況にあるといえます。
しかし、その一方で、この”全体的に良い”という評価が、かえって日本の深刻な教育問題を認識しづらくしている現実もあるのです。
たしかに日本全体では、海外に比べてより多くの子どもたちが、より質の高い教育にアクセスできています。
しかし実際、日本国内をよりクローズアップして見てみると、そこにはいまだ教育機会へのアクセス・教育の質において、大きな格差があるのです。
次の項では、そのような日本の教育の問題を、その原因、背景とともに詳しく解説していきます。
日本におけるSDGs目標4の課題/日本の教育問題の現状とは?

現在日本が抱えている主な教育問題は以下の5つです。
- 家庭の貧困による教育格差
- 地域による教育格差
- 不登校・いじめの問題
- 学力テスト・受験の過度な重視
- 教員不足
この章では、これら5つの主な教育問題の現状を、その原因や背景とともに一つずつ詳しく解説していきます。
家庭の貧困による教育格差
貧困によって子どもが教育を受けられない問題は、決して途上国だけの問題ではありません。
日本でも、子どもが家庭の経済事情のために大学に進学できないケースは多くあります。
また、貧困が理由で学校以外での学習機会が制限されてしまう問題もあります。例えば、塾や家庭教師などの学習サービスが受けられない他、家に本やコンピュータがなかったり、博物館や美術館に行く機会がなかったりなど、貧困に苦しむ家庭では比較的に子どもが学習に触れる機会が少ない傾向があるのです。
たしかに日本の就学率や学力は全体的に高いですが、このように貧困に苦しむ家庭では質の高い教育へのアクセスが制限されている現状があります。そのため実際に、家庭の経済格差がそのまま学力の格差にもつながっているのです。
そして、その教育・学力の格差は、いずれ将来の子どもの収入の格差にも大きく影響します。途上国で度々問題視されている、いわゆる「貧困の連鎖」は、決して日本も他人事ではないのです。
※現在、日本の子どもの相対的貧困率は11.5%。つまり、約9人に1人の子どもが相対的貧困の家庭で暮らしているとされています。
参考:厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/14.pdf
地域による教育格差
教育格差は、貧困だけでなく、子どもが住んでいる地域によっても生まれます。
たとえお金があっても、単純に塾や家庭教師、習い事といった学習サービスがその地域に少なければ、子どもたちの教育機会へのアクセスは制限されてしまいます。特にプログラミング教育や社会教育など、より専門的な学習ができる場所は都市部に比べて地方には少ない傾向があります。
さらに教育機会だけでなく、教育の「質」でも地域の格差は否めません。特に地方では比較的教員のなり手が少ないために、都市部に比べて教員の質が低くなっていると指摘されています。また、そもそも学校や塾などの教育施設の数が少ないために、地方では質の高い教育を受けられる場所・機会の選択肢が少ないという問題もあるのです。
そして後ほどまた詳しく説明しますが、現在多くの教育問題に対して、政府や企業、NPOなどがさまざまな取り組みを行っています。しかし当然、地域によってはそれら団体の取り組みが活発でない地域もあります。そのような一部の地域で、教育問題が解決されないまま取り残されてしまっている現状も、地域による教育格差の一つです。
不登校・いじめの問題

不登校やいじめによって多くの子どもたちが教育を受けられなくなってしまうことも、日本では特に深刻な問題です。
実際、文部科学省の調査によると、不登校の生徒数は小学校・中学校合わせて約29万9000人(2022年時点)にのぼり、10年連続で増加しています。
さらに、いじめも増加傾向にあります。同じく文部科学省の調査では、小・中・高等学校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は2022年時点で合計約68万2000件となっています。同数値も、不登校と同様に近年大幅に増加しているのです。
先述の通り、日本では義務教育によってほとんどの子どもたちが小学校、中学校に通うことができています。しかしその一方で、このように不登校・いじめなどの問題によって多くの子どもたちが教育を受けられなくなっている深刻な現状もあるのです。
学力テスト・受験の過度な重視
学校や塾など、海外に比べて教育施設が充実している日本ですが、その教育の中で学力テストや受験が過度に重視されるあまり、かえって子どもたちの特定の能力を伸ばせなくなっているという問題があります。
学力テストは小学校から頻繁に行われ、中学校や高校では、受験を基にした受験のための教育が行われることも少なくありません。
そのため自分の頭で考える学習よりも、知識をより多く暗記するための「詰め込み学習」が重視される傾向があり、子どもたちの「創造性」や「主体性」、「問題解決能力」といった能力の向上を妨げています。
さらに、試験の結果が過度に重視されることで、「子どもの試験の結果=その子どもの価値」として他人や社会に認識される(また子ども自身もそう認識する)ことがあり、そのため試験結果によって子どもが自分の価値を見失ったり、試験では評価されなかった他の才能や強みが気づかれず、埋もれてしまうという問題もあります。
教員不足
最後に、学校における教員の不足も深刻な教育問題の一つです。
特に教員の過重労働やストレスなどの問題のために、若い人材が教員を目指さなくなっていることや、団塊世代の教員の退職なども重なって、教員不足の問題は近年ますます深刻になっています。
実際にその影響として、元々教員が少ない地方ではさらに教員が減少し、先ほど説明した地域による教育格差がより拡大することが懸念されています。
また都市部でも、教員の数が今よりも少なくなることで、教員一人当たりが担当する子どもの数が増え、生徒に勉強を教えたり、勉強以外で相談に乗ったりするなど、生徒一人ひとりへの対応が難しくなってしまうという問題もあるのです。
SDGs目標4の達成に向けた日本の取り組み事例

ここまで日本の深刻な教育問題について幅広く解説してきました。
最後に、それらの教育問題を解決して、日本におけるSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を達成するための実際の取り組み事例をご紹介します。
現在行われている取り組みの内容を知り、上記の教育問題の解決策を考える上でのヒントになれば幸いです。
子どもたちへの教育機会の提供
貧困や地域による教育格差、また不登校やいじめなど、さまざまな問題によって教育を受けられない子どもたちに教育の機会を提供する取り組みが行われています。
例えば、認定NPO法人Learning for Allは、学校に通えない子どもたちや学習支援が必要な子どもたちのために、オンラインで個別指導を行ったり、学習コンテンツを提供したりする取り組みを行っています。
さらに文部科学省は、「地域未来塾」という取り組みを実施し、地域の学生や教職員のOB、NPO団体などと協力して、原則無料で子どもたちに教育機会を提供する活動を行っています。
ICT教育の推進
ICT教育の大きな利点は、地域による教育格差を減らせることです。子どもがタブレットなどでデジタル教材を学習できれば、実際に学校や塾、教員の数が少ない地方の子どもでも、等しく教育機会にアクセスできるようになります。
また生徒の学習状況がデータ化されることで、より一人ひとりにあった質の高い教育を提供でき、さらに従来の紙や黒板を使った教育をICTに置き換えることで、教員の作業負担の大幅な削減にもつながります。
このICT教育は、実際すでに多くの学校で進められており、国内の9割以上の小学校・中学校がタブレットなどの端末を活用した教育を始めています(※8)。また、株式会社すららネットや、ワンダーファイ株式会社など民間の企業でも、ICT教育のためのデジタル教材を開発したり、それを学校や塾などの教育施設に提供したりする取り組みが行われています。
STEAM教育の導入
※STEAM(スティーム)教育とは、「科学(Science)」、「技術(Technology)」、「工学(Engineering)」、「芸術と教養(Art)」、「数学(Mathematics)」を教える教育のこと。
STEAM教育を導入することで、複数の面で子どもたちへの教育の質を高めることができます。
まず「技術」や「工学」の教育では、プログラミングやロボットなど、子どもたちの将来のキャリアにつながる実践的な知識・技術を学ぶことができ、同時に「科学」や「数学」、「芸術と教養」の分野でも、それぞれの知識とともに「論理的思考力」や「課題解決能力」、「創造力」といった、これまでの詰め込み教育では伸ばせなかった能力を伸ばせるようになるのです。
このSTEAM教育は、現在国内の小学校、中学校、高校などでそれぞれのレベルに合わせた形で導入され始めており、実際に埼玉大学が設置したSTEM教育研究センターは、その普及活動の一環として地域の学校でSTEAM教育の出張授業を行ったり、STEAM教育を行う教員への研修などの取り組みを行っています。
SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」日本の現状まとめ|私たちにできること

このように、就学率や学力など、海外に比べて全体的に良い状況にあるとされる日本の教育ですが、実際に国内の教育現場をより注視してみると、そこには教育格差や不登校、試験偏重のカリキュラム、そして教員不足といった深刻な問題も多く存在しています。
そして、それらの問題を解決するために、政府や企業、NPOなどが、それぞれの教育現場で様々な取り組みを行っています。
ではそんな中、教育問題を解決するために私たちにできることはなんでしょうか。
もし、今皆さんが学生や教師など、教育現場に直接関わっている立場であれば、例えば実際に教育格差やいじめなどさまざまな理由で学習が遅れている生徒のサポートをしたり、またそのサポートのための仕組みを作ったりすることができるかもしれません。
あるいは現場にいなくても、実際に教育問題に取り組んでいる団体に寄付やボランティアをすることで、間接的にその問題解決に貢献することもできます。
日本の教育の現状に関するまとめ
日本のSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」は、就学率や学力面で世界トップクラスの状況にありますが、その一方で「家庭の貧困による教育格差」「地域による教育格差」「不登校・いじめ」「学力偏重教育」「教員不足」といった深刻な課題が存在しています。これらの問題解決に向けて、政府、企業、NPOが「教育機会の提供」「ICT教育の推進」「STEAM教育の導入」などの取り組みを進めています。私たち一人ひとりも、教育支援や寄付・ボランティアを通じて問題解決に貢献できるのです。
update: 2024.12.17




