
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」とは?世界と日本の現状と取り組みをわかりやすく解説
update: 2025.11.15
Contents
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」とは?世界と日本の現状と取り組みをわかりやすく解説
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」は、森林保全や砂漠化防止、生物多様性の保護を通じて、地球上の生命を守る重要な目標です。世界では年間約470万ヘクタールの森林が失われ、生物多様性は過去50年で73%も減少しています。この記事では、目標15の意味や背景、世界と日本の具体的な取り組み、そして私たち一人ひとりができることをわかりやすく解説します。

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」とは
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」は、地球上の陸域生態系を守り、森林を適切に管理し、砂漠化を防ぎ、生物多様性の損失を食い止めることを目指す国際的な目標です。
SDGs目標15の基本情報と目的
SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」は、陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止することを目標としています。
この目標は、2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標の一つとして、2030年までの達成を目指しています。特に、森林や湿地、乾燥地、山地などの陸上生態系を保全し、その持続可能な利用の回復を狙いとしたものです。
目標15には12個のターゲット(具体的な達成目標)が設定されており、森林保全から生物多様性の保護まで幅広い内容が含まれています。これらは相互に関連し合いながら、陸の豊かさを総合的に守ることを目指しています。
「陸の豊かさ」とは何を指すのか
「陸の豊かさ」とは、森林、湿地、山地、乾燥地などの陸上生態系と、そこに生息する多様な動植物、さらには土壌や水資源などを含む包括的な概念です。
森林、草原、砂漠等、様々な地形からなる陸上の生態系は、地球上の約30%を覆っており、私たち人間が生活を営むために欠かすことのできない食料・燃料・医療品等のすべての供給源となっています。
陸の豊かさには、目に見える動植物だけでなく、土壌中の微生物や昆虫、きのこなどの菌類も含まれます。これらすべてが複雑に絡み合い、相互に依存しながら生態系を形成しています。人間もまた、この生態系の一部として、陸の豊かさから多くの恩恵を受けて生活しています。
森林・生態系・生物多様性の関係
森林は地球の生命を支える重要な基盤であり、生態系の中心的な役割を果たしています。人が生活をするのに欠かせない食料は、8割以上を植物から摂取しています。
森林は酸素を生み出し、二酸化炭素を吸収することで気候を調整しています。また、雨水を蓄え、洪水を防ぎ、土壌の流出を防ぐ役割も担っています。さらに、地球上では確認されているだけでも175万種類の生き物がいますが、その多くが森林を生息地としています。
生物多様性は、このような多様な生き物たちが相互に関わり合いながら生きている状態を指します。一つの種が失われると、それに依存していた他の種にも影響が及び、生態系全体のバランスが崩れる可能性があります。森林・生態系・生物多様性は密接につながっており、どれか一つでも失われると、私たちの生活基盤そのものが脅かされることになります。

なぜ「陸の豊かさ」を守る必要があるのか
陸の豊かさは、私たち人間の生存と豊かな暮らしを支える基盤です。しかし今、森林破壊や砂漠化、生物多様性の損失により、その基盤が危機に瀕しています。
森林伐採や砂漠化が進む現状
世界の森林面積は2010年から2020年の間に年平均470万ヘクタールずつ減少しています。これは日本の国土面積の約8分の1に相当する広さです。1990年から2000年の間は年平均780万ヘクタールの減少でしたので、減少速度は鈍化傾向にあるものの、依然として深刻な状況が続いています。
砂漠化の問題も深刻です。毎年1,200万ヘクタール、毎分23ヘクタールの土地が砂漠化により失われています。現在、約20億人が砂漠化の最も進行しやすい乾燥地帯に暮らしており、2050年までに人口の4分の3が水不足に直面すると予想されています。
砂漠化の原因は、過放牧、過度な農地開発、森林伐採などの人為的要因と、気候変動による干ばつなどの気候的要因が複雑に絡み合っています。特にアフリカのサヘル地域、中国、インド、モロッコなどで砂漠化が急速に進行しています。

生態系のバランスが崩れると何が起こる?
生態系のバランスが崩れると、まず生物多様性が失われます。WWFの報告によると、1970年から2020年までの50年間で、野生動物の個体群の大きさが平均73%も減少しています。これは野生生物の数が3分の1以下になったという衝撃的な数字です。
森林が失われることで、二酸化炭素の吸収能力が低下し、地球温暖化が加速します。また、森林が持つ水源涵養機能が失われることで、洪水や土砂災害のリスクが高まります。土壌の劣化により農業生産性が低下し、食料不足につながる可能性もあります。
さらに、生態系の崩壊は新たな感染症の発生リスクも高めます。森林破壊により野生動物と人間の接触機会が増えることで、動物由来の感染症が人間に感染する可能性が高まるのです。
人間社会への影響(食料・水・気候変動など)
陸の豊かさの損失は、人間社会に直接的な影響を及ぼします。まず食料生産への影響が深刻です。土地の劣化により、世界の農地の52%が影響を受けており、26億人以上の生活が脅かされています。
水資源への影響も重大です。森林が失われることで、地下水の涵養能力が低下し、きれいな水の供給が困難になります。すでに多くの地域で水不足が深刻化しており、将来的にはさらに多くの人々が水ストレスに直面することが予想されています。
気候変動への影響も無視できません。森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出は、人為的な排出量の約1割を占めています。また、砂漠化により農業が営めなくなった人々は、都市部への移住や難民化を余儀なくされ、社会的な不安定要因となっています。
世界での主な取り組み事例

陸の豊かさを守るため、国際機関や各国政府、民間団体などが様々な取り組みを展開しています。
国連・世界銀行などの国際的枠組み
国連では、砂漠化対処条約(UNCCD)を通じて、砂漠化に直面する国々への支援を行っています。この条約は、深刻な干ばつや砂漠化に直面する地域の開発支援を目的とし、過放牧や森林伐採に代わる収入機会の援助、植林などの回復活動、持続可能な森林管理の提案を実施しています。
国連開発計画(UNDP)は、グリーン・コモディティ・プログラムを展開しています。これは、パーム油、牛肉、大豆、ココア、コーヒーなど、環境への影響が大きい農産物の生産を、より持続可能な形に転換することを目指すプログラムです。現地政府機関の人材育成、農家組織の強化、生態系と生物多様性保護を目指した農法への転換支援などを行っています。
世界銀行も森林保全プロジェクトへの資金提供を積極的に行っており、途上国の森林管理能力向上や、地域コミュニティの参画促進などを支援しています。
森林減少を防ぐ国際プロジェクト(例:REDD+)
REDD+(レッドプラス)は、途上国の森林減少・劣化による温室効果ガス排出を削減する画期的な仕組みです。森林を伐採するよりも保全する方が経済的価値が高くなるよう、先進国が途上国に経済的インセンティブを提供します。
REDD+では、森林減少・劣化の抑制だけでなく、森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増強も含まれています。国連食糧農業機関(FAO)、国連開発計画(UNDP)、国連環境計画(UNEP)が共同で、65カ国でREDD+プログラムの設計・実施支援を行っています。
2017年からは緑の気候基金(GCF)が、REDD+活動による排出削減に対して、CO2換算で1トンあたり5ドルの成果支払いを行うパイロットプログラムを開始しました。すでに中南米7件、アジア1件の計8件が採択され、具体的な成果を上げています。
各国の具体的な取り組み(ブラジル、インドネシアなど)
ブラジルでは、アマゾン熱帯雨林の保護に向けた取り組みが進められています。衛星モニタリングシステムを活用した違法伐採の監視や、保護区の設定、持続可能な森林管理の推進などが行われています。また、農業と森林保全を両立させる「アグロフォレストリー」の普及も進んでいます。
インドネシアでは、世界最大規模のマングローブ植林プロジェクトが実施されています。10万ヘクタール以上のマングローブ林が再生され、沿岸地域の保護と生物多様性の回復に貢献しています。また、パーム油産業における持続可能な生産方式への転換も進められています。
中国では「三北防護林プロジェクト」という大規模な植林プロジェクトが推進されています。砂漠化の進行を食い止めるため、中国北部に巨大な緑の長城を築く計画で、すでに数百万ヘクタールの植林が実施されています。ただし、単一樹種の大規模植林による水不足などの新たな課題も生じており、より生態系に配慮した植林方法への転換が求められています。
日本での取り組み事例

日本は国土の約7割を森林が占める森林大国として、独自の森林保全政策と国際協力を展開しています。
国レベルの政策(森林保全・里山の再生など)
林野庁を中心に、森林・林業基本計画に基づく持続可能な森林管理が推進されています。間伐の促進、再造林の推進、森林経営管理制度の運用など、森林の多面的機能を発揮させるための施策が実施されています。
環境省では、生物多様性国家戦略を策定し、里山イニシアティブを推進しています。里山は、人の手が適度に加わることで維持されてきた日本独特の生態系です。里山の保全・再生を通じて、生物多様性の保全と持続可能な利用の両立を目指しています。
2019年からは森林環境税が導入され、年間約600億円の財源が確保されました。これにより、手入れの行き届かない森林の整備や、担い手の育成、木材利用の促進などが進められています。また、国産材の利用促進を図る「木づかい運動」も展開され、「ウッド・チェンジ」を合言葉に、木材利用の意義を広める活動が行われています。
企業・自治体の取り組み(CSR・地域環境活動)
多くの企業がCSR活動の一環として森林保全に取り組んでいます。社有林の持続可能な管理、植林活動の実施、FSC認証製品の調達推進など、様々な形で貢献しています。
自治体レベルでは、企業と連携した森づくり活動が活発です。企業が資金や人材を提供し、自治体が場所や技術指導を提供する「企業の森」制度が全国で展開されています。また、地域の森林資源を活用した地域活性化の取り組みも進んでいます。
建設業界では、CLT(直交集成板)などの新たな木質材料の活用が進み、都市の木造化・木質化が推進されています。公共建築物での木材利用も促進され、学校や庁舎などで積極的に木材が使用されるようになりました。
教育現場でのSDGs学習や地域プロジェクト
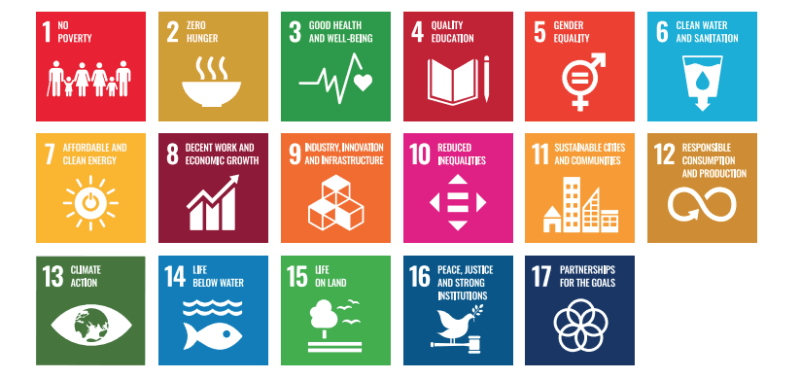
文部科学省では、ESD(持続可能な開発のための教育)の一環として、森林環境教育を推進しています。小中学校では、総合的な学習の時間を活用した森林体験学習や、学校林を活用した実践的な環境学習が行われています。
「木育」の取り組みも全国で広がっています。子どもから大人まで全ての人を対象に「木とふれあい、木に学び、木と生きる」活動が展開され、木のおもちゃに触れる体験や木工ワークショップなどが実施されています。
地域では、NPOや森林ボランティア団体による里山保全活動が活発です。市民参加型の森づくりイベントや、間伐材を活用した製品づくり、森林セラピーなど、森林を活用した多様な活動が展開されています。これらの活動は、地域コミュニティの活性化にもつながっています。
私たちにできる「陸の豊かさを守る」行動
陸の豊かさを守るために、私たち一人ひとりができることがたくさんあります。日常生活の中で実践できる具体的な行動を紹介します。
日常生活でできること(紙の節約・植林・エシカル商品)

まず身近なところから、紙の使用を見直してみましょう。不要な印刷を控え、裏紙を活用し、電子媒体で代用できるものは切り替えることで、森林資源の節約につながります。ティッシュペーパーやトイレットペーパーは再生紙製品を選ぶのも効果的です。
植林活動への参加も重要な貢献です。地域の植樹イベントに参加したり、森林ボランティアに登録したりすることで、直接的に森林保全に関わることができます。また、自宅の庭やベランダで植物を育てることも、小さいながら生態系への貢献となります。
エシカル商品の選択も大切です。環境に配慮して生産された商品、地元で作られた商品、伝統工芸品などを選ぶことで、持続可能な生産と消費を支援できます。買い物の際は、本当に必要なものかを考え、長く使えるものを選ぶことも重要です。
買い物で選ぶ(FSC認証・フェアトレードなど)
FSC認証製品を選ぶことは、森林保全への直接的な貢献となります。FSC認証は、適切に管理された森林から生産された木材製品であることを証明するマークです。ノート、コピー用紙、ティッシュペーパー、家具など、多くの製品にFSC認証マークが付いています。
フェアトレード商品の購入も重要です。コーヒー、チョコレート、紅茶などのフェアトレード認証商品を選ぶことで、途上国の生産者に適正な対価が支払われ、環境に配慮した生産方法が促進されます。
日本の木材製品を選ぶことも森林保全につながります。国産材を使用することで、日本の森林の適切な管理が促進され、輸送による環境負荷も軽減できます。家具や建材を選ぶ際は、産地を確認し、できるだけ地元産や国産材を選びましょう。
子どもと一緒にできる自然体験・環境学習
子どもたちと一緒に自然の中で過ごす時間を増やしましょう。森林公園や里山での散策、昆虫観察、植物採集など、自然と触れ合う機会を作ることで、子どもたちの環境意識が自然に育まれます。
家庭でできる環境学習も効果的です。絵本や図鑑を使って森林や生き物について学んだり、環境問題について家族で話し合ったりすることが大切です。また、木の実や落ち葉を使った工作、押し花づくりなど、自然素材を活用した創作活動も楽しみながら学べる機会となります。
地域の環境イベントへの参加もおすすめです。自然観察会、ビオトープづくり、森林整備体験など、親子で参加できるプログラムが各地で開催されています。これらの活動を通じて、地域の自然を知り、守る意識が育まれます。
「陸の豊かさ」と他のSDGsとの関わり
SDGs目標15は、他の目標と密接に関連しており、統合的なアプローチが必要です。
気候変動(目標13)との関係

森林は地球の気候システムにおいて重要な役割を果たしています。森林は二酸化炭素を吸収・貯蔵する「炭素の貯蔵庫」であり、地球温暖化の緩和に貢献しています。しかし、森林破壊により、貯蔵されていた炭素が大気中に放出され、温暖化が加速します。
気候変動は森林にも深刻な影響を与えます。気温上昇により森林火災のリスクが高まり、干ばつにより樹木の枯死が進みます。また、気候変動により生物の生息適地が変化し、生態系のバランスが崩れる可能性があります。
このように、森林保全と気候変動対策は表裏一体の関係にあります。REDD+のような、森林保全を通じた気候変動対策の取り組みが重要性を増しています。両方の課題に同時に取り組むことで、相乗効果が期待できます。
海の豊かさ(目標14)とのつながり

陸と海の生態系は、水を通じて密接につながっています。森林から流れ出る養分を含んだ水は、河川を通じて海に注ぎ、海洋生態系を支えています。この「森は海の恋人」という言葉に表されるように、豊かな森が豊かな海を育てます。
森林破壊により土砂が流出すると、河川や沿岸域の水質が悪化し、サンゴ礁などの海洋生態系に悪影響を与えます。また、マングローブ林のような沿岸域の森林は、陸と海の境界で両方の生態系を支える重要な役割を果たしています。
陸域と海域を一体的に保全することで、より効果的な生態系の保護が可能となります。流域全体を視野に入れた総合的な管理が求められています。
貧困・飢餓・平和の目標との関連性
森林資源に依存して生活する人々は、世界で約16億人にのぼります。これらの人々にとって、森林の減少は生活基盤の喪失を意味し、貧困の深刻化につながります。
土地の劣化により農業生産性が低下すると、食料不足が生じ、飢餓のリスクが高まります。また、水資源や森林資源を巡る争いが、地域紛争の原因となることもあります。
持続可能な森林管理と土地利用は、貧困削減、食料安全保障、平和構築のすべてに貢献します。SDGsの目標は相互に関連しており、統合的なアプローチによってのみ、持続可能な社会の実現が可能となります。
これからの課題と私たちの未来
2030年まであとわずか。陸の豊かさを守るために、今こそ行動を加速させる時です。
国際的な目標達成に向けた課題
2030年までにSDGs目標15を達成するには、多くの課題が残されています。森林減少の速度は鈍化傾向にあるものの、依然として年間470万ヘクタールの森林が失われています。このペースでは、2030年までの目標達成は困難です。
資金不足も大きな課題です。森林保全に必要な資金と、実際に投入されている資金との間には大きなギャップがあります。特に途上国では、森林保全と経済発展のバランスを取ることが難しく、国際的な支援の拡充が急務です。
また、違法伐採や野生生物の密猟・密輸など、法執行の強化も必要です。国際的な協力体制を強化し、持続可能でない取引を根絶することが求められています。
企業・個人が果たす役割の拡大
企業の役割はますます重要になっています。サプライチェーン全体での環境負荷の把握と削減、持続可能な調達の推進、森林保全への投資など、企業の積極的な取り組みが期待されています。
ESG投資の拡大により、環境に配慮した経営が企業価値に直結するようになりました。投資家や消費者からの圧力も高まっており、企業は環境対応を経営の中核に据える必要があります。
個人の役割も拡大しています。消費者の選択が企業行動を変える力を持っています。環境に配慮した商品を選び、持続可能なライフスタイルを実践することで、社会全体を変革する原動力となることができます。
持続可能な社会のために今できること
持続可能な社会の実現には、今すぐの行動が必要です。まず、身近なところから始めましょう。エコバッグの使用、節水・節電、リサイクルの徹底など、日常生活の中でできることはたくさんあります。
地域コミュニティでの活動も重要です。地域の環境保全活動に参加し、周りの人々と環境について話し合い、行動の輪を広げていくことが大切です。SNSなどを活用した情報発信も、意識啓発に効果的です。
次世代への教育も欠かせません。子どもたちに自然の大切さを伝え、環境を守る意識を育てることは、持続可能な未来への最も確実な投資です。今の私たちの選択と行動が、未来の地球の姿を決定づけます。

まとめ|一人ひとりの行動が地球の未来を変える
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」の達成に向けて、私たち一人ひとりができることを実践していきましょう。
目標15の重要ポイントの振り返り
SDGs目標15は、森林保全、砂漠化防止、生物多様性の保護を通じて、地球上の生命を守る重要な目標です。森林は私たちに食料、水、空気、資源を提供し、気候を調整し、多様な生き物の住処となっています。
しかし現在、世界では年間470万ヘクタールの森林が失われ、生物多様性は過去50年で73%も減少しています。この危機的状況を改善するため、国際機関、各国政府、企業、市民社会が協力して取り組んでいます。
日本でも、森林環境税の導入、企業のCSR活動、教育現場での環境学習など、様々な取り組みが進められています。私たち一人ひとりも、日常生活の中でFSC認証製品を選んだり、紙を節約したり、自然体験活動に参加したりすることで、貢献できます。
「知ること」から始めるSDGsへの第一歩
まずは「知ること」から始めましょう。森林や生物多様性の現状を理解し、なぜ守る必要があるのかを学ぶことが第一歩です。本やインターネット、環境イベントなどを通じて、正しい知識を身につけましょう。
次に「選ぶこと」を意識しましょう。買い物の際は環境に配慮した商品を選び、企業の環境への取り組みを評価基準に加えることで、持続可能な社会づくりに参加できます。
そして「伝えること」も大切です。学んだことを家族や友人と共有し、SNSで発信し、環境の大切さを広めていきましょう。小さな行動の積み重ねが、大きな変化を生み出します。地球の未来は、私たち一人ひとりの今日の選択にかかっています。
update: 2025.11.15




