
こども食堂とは?基本から支援方法まで徹底解説
update: 2025.9.21
Contents
こども食堂とは?基本から支援方法まで徹底解説
こども食堂とは何か?定義から社会的意義まで完全ガイド
「こども食堂」という言葉を耳にしたことはあるけれど、具体的にどんな場所なのかよくわからない――そんな方も多いのではないでしょうか。
こども食堂とは、子どもたちに栄養のある食事を提供するとともに、安心して過ごせる居場所をつくる地域の取り組みです。近年は全国に広がり、子どもの貧困対策や孤食の解消、さらには地域の交流拠点としても注目されています。
この記事では、こども食堂の意味や目的、現状と課題、支援の方法や具体的な事例、今後の展望までをわかりやすく解説します。
「こども食堂に関わりたい」「支援してみたい」と考えている方はもちろん、社会問題としての背景を知りたい方にも役立つ内容です。
こども食堂とは?基本的な意味と概要
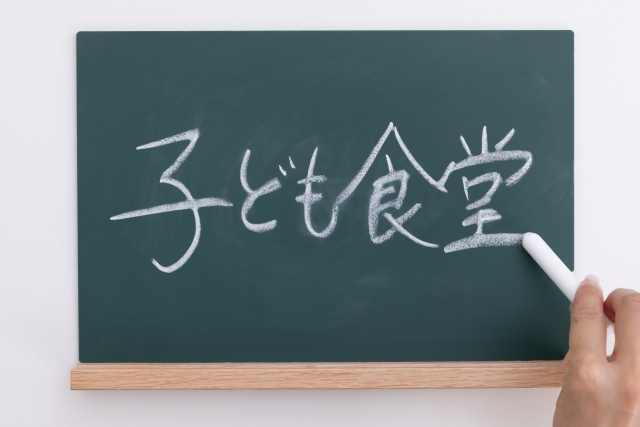
こども食堂の定義
こども食堂とは、地域の子どもたちやその家族に無料または低価格で食事を提供する地域密着型の取り組みです。単に食事を提供するだけでなく、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりや、地域住民との交流促進も重要な目的となっています。
参照:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえによると、こども食堂は「子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂」と定義されています。実際の運営形態は多様で、公民館や学校、お寺、商店街の空き店舗など、様々な場所で開催されています。参加者は子どもだけでなく、保護者や高齢者も含まれることが多く、世代を超えた地域コミュニティの拠点としての意味も持っています。
発祥と歴史的背景
日本におけるこども食堂の発祥は、2012年に東京都大田区で始まった「気まぐれ八百屋だんだん こども食堂」が最初とされています。当時、八百屋を営んでいた近藤博子さんが、近所の小学校の副校長から「給食以外の食事はバナナ一本で過ごす子どもがいる」という話を聞き、「子どもが一人で入っても大丈夫な場所」という意味を込めて「こども食堂」を開始しました。
参照:https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1910_chosa02.html
この取り組みがメディアで紹介されると全国的な注目を集め、2013年頃から各地でこども食堂が開設され始めました。特に2014年の「子どもの貧困対策法」施行を機に、社会全体で子どもの貧困問題への関心が高まり、こども食堂の設立が加速しました。
全国に広がる現状と規模
こども食堂の数は年々増加しており、2024年度の確定値では全国に10,867箇所存在し、これは公立の中学校・義務教育学校を合わせた9,265校を上回る数となっています。都市部だけでなく、地方においても積極的な取り組みが見られ、全国47都道府県すべてにこども食堂が設置されています。
参照:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000044382.html
運営形態も多様化しており、NPO法人や地域のボランティア団体、宗教法人、企業、自治体など、様々な主体が運営に携わっています。また、コロナ禍を機に、弁当配布やフードパントリー(食材配布)といった新たな支援形態も生まれ、地域のニーズに応じた柔軟な運営が行われています。
なぜこども食堂が必要なのか

子どもの貧困と食の問題
厚生労働省が2023年に公表した報告書によると、日本の子どもの相対的貧困率は11.5%(2021年)で、約9人に1人の子どもが相対的貧困状態にあります。この背景には、ひとり親世帯の増加や非正規雇用の拡大があり、特に食費の削減は家計への影響が大きく、子どもの栄養不足や偏食につながりやすい問題となっています。
経済的な理由で十分な食事を摂れない子どもたちにとって、こども食堂は重要な栄養源となります。また、食材購入の負担軽減により、家計全体の安定にも寄与し、子育て世帯の経済的ストレス軽減にもつながっています。
孤食・家庭環境の変化
核家族化の進行や共働き世帯の増加により、子どもが一人で食事をする「孤食」が社会問題となっています。孤食は栄養バランスの偏りだけでなく、食事マナーの習得機会の減少や、家族とのコミュニケーション不足にもつながります。
こども食堂では、みんなで一緒に食事をすることで、食事の楽しさや大切さを学ぶ機会を提供しています。また、調理や配膳の手伝いを通じて、食に関する知識や技能を身につけることもできます。
地域コミュニティの希薄化
都市部を中心とした地域コミュニティの希薄化により、子どもたちが地域の大人と接する機会が減少しています。この状況は、子どもの社会性の発達や、困った時の相談相手の確保に影響を与えています。
こども食堂は、子どもたちと地域住民が自然に交流できる場として機能し、地域全体で子どもを見守る環境づくりに貢献しています。特に、学校や家庭以外の「第三の居場所」として、子どもたちの健全な成長を支える重要な役割を果たしています。
こども食堂の役割とメリット

栄養のある食事を提供する場
こども食堂の最も基本的な役割は、栄養バランスの取れた食事を提供することです。多くのこども食堂では、管理栄養士の指導を受けたり、地域の食材を活用したりして、成長期の子どもたちに必要な栄養素を考慮したメニューを提供しています。
また、食事を通じて正しい食習慣や食文化を伝える「食育」の場としても機能しています。季節の食材を使った料理や郷土料理の紹介により、子どもたちの食への関心を高め、健康的な食生活の基礎を築いています。
安心できる居場所づくり
こども食堂は、子どもたちにとって安心して過ごせる居場所としての意味を持っています。家庭や学校で困難を抱える子どもたちが、プレッシャーを感じることなく自然体でいられる環境を提供しています。
スタッフやボランティアの温かい見守りにより、子どもたちは自己肯定感を高めることができ、学習支援や相談対応を通じて、総合的な成長支援を受けることができます。特に、学校になじめない子どもや不登校の子どもにとって、貴重な社会参加の機会となっています。
地域交流・世代間交流の促進
こども食堂は、異なる年齢層や立場の人々が自然に交流できる場として、地域コミュニティの活性化に貢献しています。子どもたちは様々な大人との関わりを通じて社会性を身につけ、大人たちは子どもとの交流により地域への愛着を深めています。
高齢者ボランティアが昔の遊びや文化を子どもたちに教える活動や、中高生が小学生の宿題を手伝う取り組みなど、世代間の知識や経験の伝承も行われています。これらの交流は、地域全体の結束力向上にもつながっています。
子どもの成長や学びを支える効果
多くのこども食堂では、食事提供と併せて学習支援を行っており、子どもたちの学力向上や進路選択をサポートしています。大学生ボランティアや退職した教員が指導にあたることで、個別のニーズに応じた丁寧な支援が可能となっています。
また、調理体験や農業体験、読み聞かせなど、学校では体験できない多様な活動を通じて、子どもたちの好奇心や創造力を育んでいます。これらの体験は、子どもたちの将来の可能性を広げる重要な機会となっています。
こども食堂の運営の実態

運営主体(NPO・地域住民・自治体など)
こども食堂の運営主体は多様で、地域住民による任意団体、NPO法人、社会福祉法人、宗教法人、企業、自治体直営など、地域の特性や資源を活かした運営形態が選択されています。
近年は、企業のCSR活動の一環として運営される事例や、自治体が直接運営する公設民営型の事例も増加しています。また、複数の団体が連携して運営する協働型の取り組みも見られ、持続可能な運営を目指す工夫が各地で行われています。
利用対象者と費用
こども食堂の利用対象者は「地域の子どもならだれでも」としている場合が多く、経済状況や家庭環境による制限を設けていないのが一般的です。子どもの利用料金は無料から数百円程度、大人は数百円程度に設定されている場合が多く、参加しやすい価格設定となっています。
事前申し込みは不要な場合が多く、気軽に参加できる雰囲気づくりが重視されています。ただし、食材準備の都合上、事前登録制を採用している食堂もあり、運営方針により様々な形態が見られます。
開催場所・頻度・提供されるメニュー
開催頻度は月1回が最も多く、次いで2週間に1回、週1〜2回と続きます。運営者側からも「月1回のペースなら、気負わず無理なく、長く続けられる」との声もあります。
提供されるメニューは、カレーライスやハンバーグ、唐揚げなど子どもが好む料理が中心ですが、栄養バランスを考慮したメニュー構成が心がけられています。季節の食材を活用した料理や、地域の特産品を使った郷土料理を提供する食堂も多く、食育の観点も重視されています。
こども食堂が抱える課題
資金不足と人材不足
多くのこども食堂が直面している最大の課題は資金不足です。食材費、会場費、光熱費などの運営費用を、寄付や助成金、参加費のみで賄うのは困難で、運営者の自己負担に依存している場合も少なくありません。
認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえによる2024年9月の調査では、「物価上昇による影響を感じている」という回答が88.5%と9割近くを占めており、運営の継続に大きな影響を与えています。
人材不足も深刻な問題で、調理スタッフ、配膳スタッフ、子どもの見守りスタッフなど、様々な役割を担うボランティアの確保が課題となっています。特に平日開催の場合は、平日に活動できるボランティアの確保が困難で、運営の継続性に影響を与えています。
参照:https://musubie.org/news/grant/10211
運営の継続性の難しさ
こども食堂の運営は、多くの場合ボランティアの善意と献身に支えられていますが、中心となるスタッフの高齢化や転居、体調不良などにより運営が困難になるケースがあります。また、新型コロナウイルスの影響で一時休止を余儀なくされた食堂も多く、外部環境の変化への対応力も課題となっています。
組織体制の整備や後継者の育成、運営ノウハウの共有など、持続可能な運営モデルの確立が急務となっています。
利用者への周知と参加しやすさの課題
農林水産省のアンケート調査による結果では、「来て欲しい家庭の子どもや親に来てもらうことが難しい」という問題が全体の42.3%と一番大きなウェイトを占めています。本当に支援を必要とする家庭にこども食堂の情報が届いていない、という課題があります。
また、「貧困世帯向け」というイメージを持たれることで、利用をためらう家庭もあります。「みんなの食堂」「地域食堂」といった名称変更や、イベント性を持たせた運営により、参加への心理的ハードルを下げる工夫が求められています。
衛生管理や安全面での懸念
食事を提供する以上、食中毒などの衛生管理面でのリスクは避けられません。多くのボランティアが調理に関わるため、衛生管理の知識や技術の統一が課題となっています。
また、子どもの安全確保や、アレルギー対応なども重要な課題です。事故防止のための体制整備や、緊急時の対応マニュアルの作成、保険加入など、安全面での対策強化が求められています。
こども食堂を支援する方

ボランティアとして参加する
こども食堂への最も直接的な支援方法は、ボランティアとして参加することです。調理、配膳、片付け、子どもの見守り、学習支援など、様々な活動があり、自分の時間や能力に応じて参加することができます。
特に、調理経験者、保育・教育経験者、医療・福祉関係者などの専門知識を持つ方の参加は大変歓迎されます。また、大学生や高校生の参加も増えており、子どもたちとの年齢が近いことで、良い兄姉的存在として機能しています。
寄付やクラウドファンディングで支える
金銭的な支援として、寄付やクラウドファンディングを通じた支援があります。継続的な支援としてマンスリー寄付を設定している食堂もあり、安定した運営に寄与しています。
食材や日用品の現物寄付も重要な支援です。お米や調味料、野菜、冷凍食品などの食材のほか、食器や調理器具、衛生用品なども必要とされています。企業からの大口寄付や、農家からの野菜提供なども各地で行われています。
企業や自治体による協力事例
企業による支援では、食材の提供、会場の無償貸与、社員ボランティアの派遣、運営費の助成などが行われています。コンビニエンスストアによる廃棄食品の提供や、レストランチェーンによる調理ノウハウの提供なども実施されています。
自治体による支援では、運営費の助成、会場の提供、広報支援、食品衛生講習の実施などがあります。また、子育て支援や貧困対策の一環として、こども食堂と連携した総合的な支援体制を構築している自治体も増加しています。
こども食堂の具体的な事例紹介
都市部での取り組み
東京都新宿区では、多国籍の子どもたちが多い地域特性を活かし、様々な国の料理を提供することで文化交流を促進するこども食堂があります。また、外国人保護者向けの日本語教室も併設し、地域の多様性を活かした運営が行われています。
大阪市では、商店街の空き店舗を活用し、平日は学習支援、土日は食事提供を行う複合型運営を実施する事例があります。地域商店街との連携により、子どもたちの職業体験の機会も提供しています。
地方での成功例
島根県出雲市では、地元農家との連携により、新鮮な地元野菜を使った料理を提供するこども食堂があります。子どもたちには農業体験の機会も提供し、食と農業の大切さを学ぶ食育活動も行っています。
北海道旭川市では、市内の複数のこども食堂が連携し、情報共有やボランティアの相互派遣を行うネットワークが形成されています。この連携により、運営の安定化と質の向上を実現しています。
特徴的な活動や新しい試み
コロナ禍を機に始まった「配食型こども食堂」では、感染リスクを避けながら支援を継続するため、弁当の配布やフードパントリー(食材配布)を実施しています。この取り組みにより、これまで来所が困難だった家庭にも支援の手を差し伸べることができました。
オンライン学習支援と連携したハイブリッド型運営や、移動こども食堂による山間部への出張サービスなど、地域のニーズや環境に応じた革新的な取り組みも各地で展開されています。
政策・社会とのつながり

子どもの貧困対策としての位置づけ
2014年に施行された「子どもの貧困対策法」では、教育支援、生活支援、就労支援、経済的支援の4つの柱が掲げられており、こども食堂は主に生活支援の一環として位置づけられています。
内閣府の「子どもの貧困対策に関する大綱」では、地域における学習支援や居場所づくりの重要性が明記されており、こども食堂はその中核的な取り組みとして評価されています。また、2019年の法改正では、子どもの将来だけでなく現在の生活も支援対象として明確化され、こども食堂の意義がより重視されるようになりました。
SDGsとの関連性
こども食堂の活動は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の複数の目標達成に貢献しています。特に「1. 貧困をなくそう」「2. 飢餓をゼロに」「3. すべての人に健康と福祉を」「4. 質の高い教育をみんなに」「11. 住み続けられるまちづくりを」との関連が深く、地域レベルでのSDGs推進の具体的な取り組みとして注目されています。
企業のSDGs経営の一環としてこども食堂を支援する事例も増加しており、社会的課題の解決と企業価値の向上を両立する取り組みとして評価されています。
自治体や国の支援制度
国レベルでは、厚生労働省の「地域子どもの未来応援交付金」や「子ども・子育て支援交付金」により、こども食堂を含む子どもの居場所づくりに対する財政支援が行われています。
多くの自治体では独自の支援制度を設けており、運営費助成、食材費補助、会場提供、広報支援などを実施しています。特に、東京都や大阪府などでは、こども食堂の設立・運営支援を目的とした専門の窓口を設置し、包括的な支援体制を整備しています。
こども食堂の今後の展望

数の拡大と質の維持
こども食堂の数は今後も増加が見込まれますが、量的拡大とともに質の維持・向上が重要な課題となります。運営者向けの研修制度の充実や、優良事例の共有システムの構築により、全国的な質の底上げを図る必要があります。
また、地域のニーズに応じた多様な運営形態の開発も求められており、従来の「月1回の食事提供」から、日常的な居場所機能や専門的な支援機能を持つ拠点型への発展も期待されています。
持続可能な運営モデルの模索
長期的な運営継続のためには、安定した財源確保と人材育成が不可欠です。企業や自治体との連携強化、社会福祉法人化による安定性向上、収益事業との組み合わせなど、様々な持続可能性向上の取り組みが検討されています。
また、デジタル技術の活用による効率化や、運営ノウハウのマニュアル化・標準化により、新規参入の敷居を下げる取り組みも重要になっています。
社会全体で取り組むための課題
こども食堂が真に社会インフラとして機能するためには、一部の善意ある人々の取り組みから、社会全体での支え合いの仕組みへと発展させる必要があります。企業の社会的責任としての参画促進、教育機関との連携強化、医療・福祉機関との協働体制構築などが求められています。
また、こども食堂の認知度向上と正しい理解の普及により、利用者・支援者双方の参加促進を図ることも重要な課題です。
まとめ|こども食堂が目指す未来
こども食堂の意義の再確認
こども食堂とは、単に食事を提供する場ではなく、すべての子どもが安心して成長できる地域社会の実現を目指す重要な取り組みです。経済格差や社会の変化により生じる様々な課題に対し、地域の力で子どもたちを支える仕組みとして、その意味と価値はますます高まっています。
栄養のある食事、温かい居場所、多様な学びの機会を提供することで、子どもたちの現在と未来を支えるこども食堂は、誰もが尊重され、支え合う共生社会の象徴的な存在といえるでしょう。
誰でもできる支援や参加の方法
こども食堂への参加や支援は、特別な資格や大きな負担を必要としません。時間のある時のボランティア参加、余った食材の寄付、SNSでの情報拡散など、それぞれができる範囲での関わりが大切です。
また、こども食堂を利用することで地域とのつながりを深めたり、自分自身や家族の居場所を見つけたりすることも、立派な社会参加の形です。支援する人、される人という一方向的な関係ではなく、お互いに支え合う関係性の中で、すべての人が生きやすい社会を築いていくことが、こども食堂が目指す真の目標なのです。
update: 2025.9.21




