
持続可能な漁業とは?海と魚の今と日本の取り組み
update: 2025.6.29
Contents
持続可能な漁業とは?海と魚の今と日本の取り組み
海の資源は無限ではありません。
近年、魚の数が減り続け、海の生態系や私たちの食生活にも影響が出始めています。こうした中で注目されているのが「持続可能な漁業」という考え方です。
この記事では、「持続可能な漁業」とは何かをわかりやすく解説し、今、海で起きている課題や、日本で進められている取り組みについてご紹介します。

持続可能な漁業とは?
持続可能な漁業とは、海の資源を守りながら、将来にわたって魚をとり続けられるようにする漁業のあり方です。
近年、世界中で魚のとりすぎ(過剰漁業)が問題となっており、魚の数が減ったり、海の生きもののバランスが崩れたりしています。このままでは、将来、魚が食べられなくなるかもしれません。
そこで注目されているのが、「持続可能な漁業」という考え方です。
魚をとりすぎないように漁獲量を制限したり、産卵期には漁をお休みしたり、海の環境を壊さない道具を使うなどの工夫が行われています。また、漁業を行う地域の人たちが協力して、自分たちの海を守る「共同管理」も広がっています。
このように、自然と人とのバランスを大切にするのが持続可能な漁業の基本です。
未来の世代にも豊かな海を残すために、今、世界中でさまざまな取り組みが進められています。
なぜ「今、持続可能な漁業」が重要なのか
世界の魚資源は危機に瀕している

世界中の海で魚が減少しています。国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、世界の水産資源のうち約35%が“とりすぎ”の状態にあります。これは過去最大の割合であり、長年にわたり魚をとり続けた影響が蓄積している証拠です。魚が減れば、漁業そのものが成り立たなくなるだけでなく、海の生態系全体にも大きな影響を及ぼします。
過剰漁業とIUU漁業の拡大
漁業の効率化が進む一方で、必要以上に魚をとる過剰漁業が深刻化しています。さらに、IUU漁業(違法・無報告・無規制)と呼ばれるルールを無視した漁業も拡大しており、持続的な資源管理を妨げています。こうした漁業は、魚の数を減らすだけでなく、真面目にルールを守って漁をしている人たちの収入や信頼を損なう原因にもなっています。
食料安全保障・環境保全・地域経済への影響
魚は世界中で重要なたんぱく源とされ、特に日本のような海に囲まれた国では食文化にも深く関わっています。魚が減ることは、私たちの食の安定(食料安全保障)を脅かすだけでなく、漁業を基盤とする地域経済の衰退や、海洋環境の悪化にもつながります。持続可能な漁業は、こうした複合的な問題を解決するカギのひとつです。
SDGsとのつながり(目標14「海の豊かさを守ろう」)

持続可能な漁業は、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)のうち、目標14「海の豊かさを守ろう」に直結しています。この目標では、2020年までに水産資源の持続的な管理や、違法漁業の撲滅などが求められており、今まさに国際社会全体で対応が進められているテーマです。つまり、海の未来を守ることは、地球全体の持続可能性に関わる大きな課題なのです。
資源管理と環境保全策

魚を守りながら漁業を続けるためには、とりすぎを防ぎ、海の環境を守る工夫が必要です。ここでは、世界や日本で行われている主な資源管理と環境保全の取り組みを紹介します。
漁獲量の管理:漁獲枠と禁漁期
魚が減りすぎないように、年間にとってよい量(漁獲枠)を決めて制限する制度があります。また、魚が産卵する時期や、まだ小さい魚が育つ時期には漁を禁止する「禁漁期」を設けることで、次の世代の魚が育ちやすい環境を整えています。
海の多様性を守る:海洋保護区と生態系アプローチ
海の一部を「海洋保護区(MPA)」として定め、そこでは漁を行わずに自然をそのまま保つことで、魚や他の生き物の住処を守ります。また、特定の魚種だけでなく、海全体のつながり(生態系)を大切にするアプローチも広がっています。
漁獲証明制度とモニタリング技術(衛星・ドローン等)
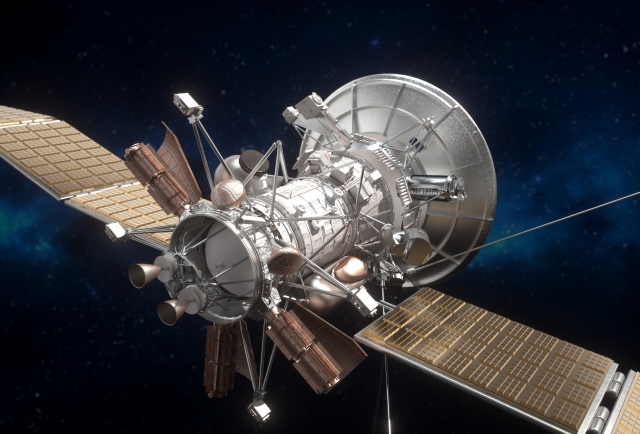
魚がどこで、誰によって、どのようにとられたかを証明する「漁獲証明制度」が広まりつつあります。また、衛星やドローンなどの技術を使って漁業の状況を監視・記録することで、ルールを守った漁が行われているかを確認しやすくなっています。
最大持続生産量(MSY)に基づいた科学的管理
「MSY(Maximum Sustainable Yield)」とは、魚を絶やさずにとり続けられる最大量のことです。この考え方に基づいて、科学的なデータをもとにした漁獲制限が行われることで、資源を長く守る仕組みが整えられています。
養殖漁業(アクアカルチャー)の持続性

天然の魚に頼るだけでなく、魚を育ててとる「養殖漁業(アクアカルチャー)」は、世界の水産物供給を支える重要な手段です。すでに私たちが食べている魚の多くが養殖によるものになっており、今後ますますその役割は大きくなると考えられています。
ただし、養殖にも課題があり、自然環境や地域社会への影響に配慮した運営が求められています。
養殖における環境課題と改善策
養殖漁業では、以下のような環境問題が指摘されています。
- 餌用に他の魚を大量に使うことで、野生の小魚の資源が減る
- 魚を狭い範囲でたくさん育てることで、病気が広がりやすくなる
- 薬品や排せつ物が海に流れ出し、水質が悪化する
- 養殖場が自然の沿岸環境を破壊することもある
これらの課題に対して、以下のような改善策が進められています。
- 魚粉に代わる植物性や昆虫由来の餌を使う
- 健康管理を徹底し、抗生物質に頼らない育て方を工夫する
- 排水処理を強化し、水質の保全に取り組む
- 地域と連携して、生態系に配慮した場所選びや運営を行う
環境と両立しながら養殖を行うことが、持続可能な水産業の鍵となります。
ASC認証など持続可能な養殖の取り組み
こうした環境・社会的な課題に対応するために、国際的に評価されているのがASC認証(Aquaculture Stewardship Council)です。
ASC認証は、「環境を守り、労働環境にも配慮した養殖」であることを示すラベルで、スーパーなどで見かけることも増えてきました。
この認証を受けるには、たとえば以下のような基準をクリアする必要があります。
- 生態系や周囲の自然に配慮した場所での養殖
- 魚の健康や福祉を守る飼育方法
- 労働者の人権・安全に配慮した雇用体制
- 地域社会との協力や説明責任のある運営
こうした仕組みを通じて、消費者も「環境や人にやさしい魚を選ぶ」という形で、持続可能な養殖を応援することができるのです。
漁業における技術革新(DX・IoT・AI)の導入事例

持続可能な漁業を実現するためには、人の努力だけでなく、テクノロジーの力も欠かせません。近年は、デジタル技術やAIを活用した「スマート漁業」が国内外で進みつつあります。こうした取り組みによって、漁業の効率化と資源管理の精度向上が同時に実現しつつあります。
スマート漁業による資源管理の最適化
スマート漁業とは、IoT(センサー技術)やAIなどを活用して、漁業をデータで最適化する取り組みです。たとえば以下のような活用が進んでいます。
- 海水温や魚群の動きをリアルタイムで把握し、漁場選びを効率化
- 漁獲した魚の種類や量を自動で記録し、資源の把握と報告作業を省力化
- ドローンや水中カメラで、海中の状況を可視化して生態系への影響をチェック
こうした技術は、とりすぎを防ぎつつ収益を高めるという、漁業者にとっても大きなメリットがあります。
衛星データやAI活用による監視と効率化
これまでは人手に頼っていた漁場の監視や漁船の動きの把握も、今では人工衛星やAIの力で精密にモニタリングできる時代になっています。
- 衛星画像で漁船の位置や密度を確認
- AIが海洋データを分析し、魚が多いエリアや漁獲量の予測をサポート
- 漁獲量の変化を長期的に追跡し、科学的な漁業管理に貢献
こうした技術によって漁業の透明性と効率性が大きく向上しつつあります。
Global Fishing Watchによる透明性の向上
世界中の漁船の動きを可視化する取り組みとして注目されているのが、Global Fishing Watch(グローバル・フィッシング・ウォッチ)です。
これは、人工衛星の位置情報をもとに、世界中の漁船の航行データをオンラインで公開するプラットフォームで、誰でもアクセスできます。
- 違法漁業の早期発見や監視強化につながる
- 政府や研究機関がデータを活用して政策や資源管理を改善できる
- NGOや市民も利用できるため、オープンな監視体制が広がっている
技術の進化によって、「海の見える化」が進み、誰もが海の資源を守る一員になれる時代が近づいています。
漁業における社会的公正と労働環境

持続可能な漁業を実現するうえで、「資源」や「環境」だけでなく、そこで働く人々の権利や暮らしを守ることも大きな課題です。とくに、国際的な水産業の現場では、労働環境や人権問題が見過ごされがちでした。近年は、サステナビリティの一環として、社会的公正(ソーシャル・サステナビリティ)にも注目が集まっています。
漁業における強制労働や人権課題
一部の国や地域では、遠洋漁業や大型漁船の現場で、長時間労働・低賃金・パスポートの取り上げなど、人権を無視した労働環境が問題視されています。とくに、外国人労働者が使い捨てのように扱われたり、劣悪な条件で働かされたりする事例が報告されています。
こうした強制労働は、倫理的に問題があるだけでなく、持続可能性の観点からも認められない行為です。企業や消費者にも、「誰が、どのように」魚をとったのかを知る責任が求められています。
グローバルな労働基準への対応
こうした課題に対応するため、国際的には以下のような労働基準や認証制度が活用されています。
- 国際労働機関(ILO)の「漁業労働に関する条約」(C188)
- 労働・人権・環境に配慮した調達を推進する「サプライチェーンデューデリジェンス」
- ASC(養殖)やMSC(漁業)の認証にも、労働環境に関する基準が組み込まれつつあります
これらは単なるチェックリストではなく、漁業の現場における人間の尊厳を守るための仕組みです。
地域社会と共に行う共同管理の重要性
漁業の現場では、地域の漁師や住民が協力して資源を守る「共同管理」も、社会的に持続可能なモデルとして注目されています。
たとえば日本の沿岸地域では、漁協を中心とした「地域ぐるみの資源管理」が進められています。地元の人々が、漁のルールや時期を自ら決め、資源を守る活動を行うことで、地域経済・文化・自然が一体となって守られる仕組みです。
共同管理は、現場の声を尊重した“顔の見える漁業”を実現する手段でもあり、国際的にも高く評価されています。
持続可能な漁業を目指すソーシャルビジネスと日本の取り組み

持続可能な漁業は、行政や漁業者だけの努力では実現できません。近年では、社会課題の解決とビジネスを両立する「ソーシャルビジネス」のかたちで、漁業の現場を支える取り組みが世界中に広がっています。日本でも地域資源を活かした持続可能な漁業モデルが動き始めています。
海外の革新的な取り組み(例:ブルー・ベンチャーズ)
マダガスカルで活動するブルー・ベンチャーズ(Blue Ventures)は、ソーシャルビジネスの先進事例として知られています。この団体は、地元の漁師たちと協力しながら、サンゴ礁保護や一時的な禁漁区の設定など、持続可能な方法での漁業管理を進めています。
特徴的なのは、現地のコミュニティ主導で意思決定が行われていること。漁獲量が回復することで、漁師の収入も安定し、保健・教育などの地域課題にも対応できるようになっています。環境・経済・福祉の三方よしを実現した成功モデルです。
日本の地域資源活用と漁業改善プロジェクト(FIP)
日本でも、地元の漁業者や自治体、民間企業、NGOが連携して、FIP(漁業改善プロジェクト)という国際的な枠組みを用いた持続可能な取り組みが始まっています。
たとえば、北海道ではホタテ漁業の改善、三陸地域ではカタクチイワシの持続的利用を目指したプロジェクトが進行中です。これらは漁獲データの見える化や資源評価の導入、サプライチェーン全体での持続可能性確保などに取り組んでいます。
FIPを通じて、地元の漁業が世界基準に近づくと同時に、国際市場での評価も高まりつつある点が注目されています。
持続可能性と地域経済の好循環
漁業資源を守ることは、自然環境のためだけではありません。持続可能な漁業を通じて、地域に安定した仕事と収入が生まれることが、漁村の未来を守るカギになります。
環境にやさしい漁を続けることで、消費者からの信頼が高まり、高付加価値な商品としてのブランディングにもつながります。さらに、ツーリズムや食育などへの広がりも期待されており、地域全体で「海を活かしたまちづくり」が進んでいます。
このような環境・経済・地域社会が支え合う循環こそが、本当の意味での持続可能な漁業と言えるのではないでしょうか。
認証制度と消費者の選択
持続可能な漁業を広げていくうえで、「どんな魚を選ぶか」という消費者の行動も大きな力になります。その判断材料として役立つのが、水産物に付けられた認証ラベルです。
MSC・ASC認証の概要と社会的意義
世界的に広まっている代表的な認証に、次の2つがあります。
- MSC認証(Marine Stewardship Council)
→ 野生の魚を対象に、持続可能な方法で漁獲されたことを示すラベル。 - ASC認証(Aquaculture Stewardship Council)
→ 養殖の魚に対して、環境や労働に配慮して育てられたことを示すラベル。

これらの認証は、資源管理・生態系保全・労働環境・地域社会との関係など、さまざまな基準をクリアした漁業や養殖業者にのみ与えられます。ラベルのついた商品を選ぶことは、漁業者の努力や環境保護を応援する意思表示でもあります。
ラベルを見て選ぶ:消費者ができる行動
スーパーや回転寿司チェーンなどでも、MSCやASCマークのついた商品が少しずつ増えてきました。これらのラベルを意識して選ぶだけでも、私たち一人ひとりが持続可能な漁業に参加することができます。
また、次のような行動もおすすめです。
- 食卓に出す魚の種類や漁獲時期に関心を持つ
- 必要以上に買いすぎず、フードロスを減らす
- 地元の漁業者が大切に育てた魚を地域で消費する
こうした日々の小さな選択が、海の未来を守る大きな一歩につながります。
企業に求められるサプライチェーンの透明性
消費者だけでなく、水産物を扱う企業や飲食店にも責任があります。どこで、どのようにとられた魚なのか、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保することが求められています。
最近では、サステナビリティを重視する企業が、認証ラベル付きの魚を優先的に仕入れたり、自社のサプライチェーンを見直したりする動きも加速しています。
企業と消費者の双方が意識を高めることで、「選ばれる漁業」が増えていき、結果として、環境と社会にやさしい水産業が定着していくのです。
LCA(ライフサイクルアセスメント)による環境評価
持続可能な漁業を実現するには、「魚をどうとるか」だけでなく、その魚が食卓に届くまでの過程すべてを通じて環境への影響を考える視点が大切です。そこで注目されているのが、LCA(ライフサイクルアセスメント)という考え方です。
水産物のライフサイクル全体での環境負荷とは
LCAとは、製品やサービスの原料調達から製造、流通、消費、廃棄までのすべての段階において、どれだけのエネルギーや資源が使われ、どのような環境負荷が発生しているかを数値化・評価する手法です。
水産業におけるLCAでは、たとえば次のような点が対象になります。
- 漁船の燃料使用量やCO₂排出量
- 養殖における飼料生産や排水による水質影響
- 冷蔵・加工・輸送にかかるエネルギーコスト
- 廃棄される魚の割合や包装資材の処理方法
「この魚は環境にやさしいのか?」を全体像から判断できるようになります。
LCAの視点を持つことは、「見えない環境負荷」に気づき、本当の意味でサステナブルな選択をするための一歩です。今後、漁業に限らず多くの産業で、LCAを活用した透明性の高いものづくり・サービスづくりが広がっていくでしょう。
まとめ:持続可能な漁業の展望と提言

漁業を持続可能なかたちに変えていくには、漁師や企業、行政だけでなく、社会全体の連携と意識の変化が欠かせません。ここでは、今後の方向性と、私たち一人ひとりにできることについて考えます。
科学・技術・社会連携による未来の漁業
これからの漁業は、科学・技術・社会が一体となって支える時代へと移行しています。
- 科学:魚の生態や資源量を正しく把握するためのデータと研究
- 技術:AI・IoT・衛星などによる資源管理の最適化と透明性の確保
- 社会:地域や漁業者、消費者が一緒にルールを作り、責任ある漁業を育てていく
さらに、環境・人権・経済のすべてに配慮した「多面的に持続可能な漁業」が求められています。未来の漁業は、ただ魚をとるだけでなく、海と人と社会が調和する持続的な仕組みでなければなりません。
持続可能な海を守るために、私たちができること
読者の一人ひとりにも、持続可能な漁業を支える行動があります。
- スーパーでMSCやASCなどの認証ラベルを意識して選ぶ
- 季節に合った魚や、地域でとれた魚を食べることで、資源を守る
- 食べきれる量を選び、食品ロスを減らす
漁業や海の問題について知り、考える機会をもつ
小さな選択でも、それが日常的に積み重なれば、海の未来を守る力になります。持続可能な漁業は、どこか遠い海の話ではなく、私たちの食卓とつながっている現実なのです。
未来の豊かな海を守るために、今日からできる一歩を一緒に踏み出しましょう。
update: 2025.6.29




