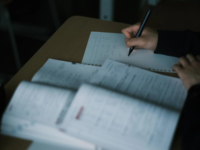【2025年最新】不登校の最新データと主な4つの原因・対策を徹底解説
update: 2025.3.23
近年、不登校の児童生徒数が急速に増加しており、社会問題となっています。その背景には様々な要因が複雑に絡み合っており、適切な支援と対策が求められています。この記事では、2025年最新のデータを交えながら不登校の現状について詳しく解説するとともに、子どもたちを支えるための具体的な対策や支援策についても紹介します。不登校に対する理解を深め、子どもたちが安心して学び、成長できる環境づくりを一緒に考えていきましょう。
【2025年最新】不登校の最新データと主な4つの原因・対策を徹底解説
不登校の定義
文部科学省によると、「不登校」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状態」にあり、年間30日以上学校を休んでいる状態であると定められています。ただし、病気や経済的な理由による欠席日数はカウントされません。
出典:児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説 | 文部科学省
ひきこもりとの違い
ひきこもりとは、職場や学校などの社会的参加を避け、原則6か月以上にわたり家に留まり続けている状態のことを指します(※1)。学校に通えない期間が長くなると社会との関わりが減り、不登校からひきこもりへと移行するケースも少なくありません。
出典:(※1)まず知ろう!「ひきこもりNOW」! | 厚生労働省
不登校の深刻な増加
文部科学省の調査によると、小中学校における不登校児童生徒数は346,482人(令和5年度)であり、過去最多を記録しました。11年連続で増加しており、今後もさらに増えることが予想されています。高校における不登校生徒数は68,770人であり、こちらも過去最多となりました。
出典:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要 | 文部科学省
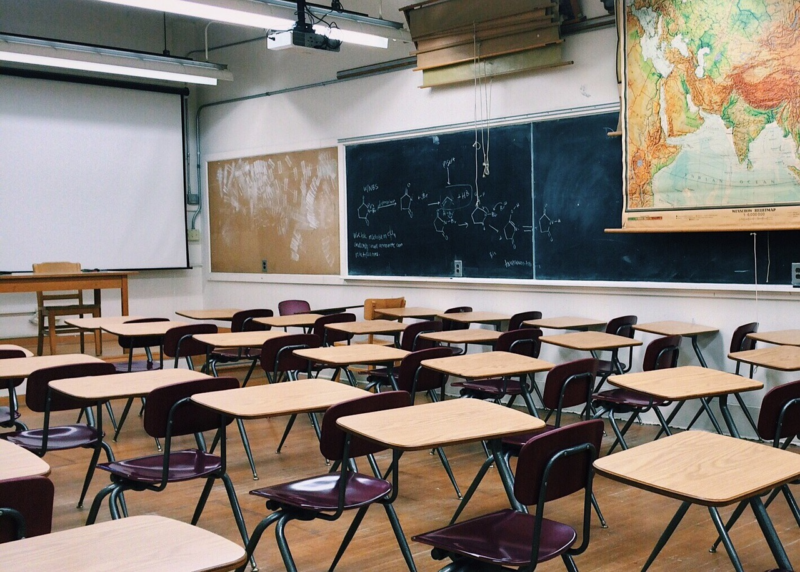
不登校の原因
不登校の原因は様々です。置かれている状況や要因は人それぞれ異なり、個々の原因を正確に把握することは容易ではありません。また、複数の要因が複雑に絡み合い、1つの原因に当てはめることが難しい場合が多くあります。こうした前提を踏まえつつ、不登校の原因となりうる要素をいくつか挙げ、解説していきます。
無気力・不安と不登校
不登校には、明確な理由がわからず、「なんとなく学校に行きたくない」と感じるケースが少なくありません。学校に行こうという気持ちはあっても、学校生活にやりがいを感じられなかったり、気力が湧かず体が動かなかったり、漠然とした不安や恐怖心から登校できなくなることがあります。こうした状況の背景には、家庭環境の問題や学力不振、生活リズムの乱れなど、さまざまな要因が関係していると考えられます。たとえば、親から十分な愛情を感じられないことによる自己肯定感の低下や、人間関係のストレスによって自律神経が乱れ、起立性調節障害を引き起こし、朝起きることが困難になるケースなどが挙げられます。
学業不振と不登校
不登校の背景には、「授業についていけない」、「成績が下がった」といった学業不振が見られる場合もあります。特に、学習内容や環境の変化が大きい小学校から中学校に上がる段階では、不登校やいじめの件数が一気に増える傾向にあり、「中1ギャップ」問題とも言われています。子どもたちが意欲的に学習に取り組めるように、小中学校の連携や授業改善、学校内外での学習支援の充実が求められています。
家庭環境と不登校
家庭環境が原因で不登校になるケースもあります。たとえば、両親の別居や離婚といった家庭環境の変化は、子どもにとって大きなストレスとなります。また、両親の不和や過干渉、無関心なども、子どもの心に大きな影響を与え、メンタルヘルスの不調につながることがあります。こうした状況によって家庭が安心できる場所ではなくなると、学校へ行く気力を失ってしまうことがあるのです。さらに、貧困により他の子どもたちと同じような学校生活を送れない場合、劣等感を抱いたり、いじめの原因となったりすることもあります。
発達障害と不登校
不登校には発達障害が関係しているケースもあります。例えば、発達障害の特性により人間関係が上手くいかなかったり、からかいやいじめに発展するケース、学習に困難を及ぼしているケース、学校の制度や部活動への不適応などが挙げられます。発達障害の可能性も考慮し、子どもたち1人1人の特性(個性)に向き合った支援・指導が必要です。
不登校による問題
不登校になると、子どもたちはどのような問題に直面するのでしょうか。ここでは、不登校がもたらし得る悪影響を3つ解説します。
将来の選択肢が狭まる
不登校になると、将来の選択肢が狭まることが懸念されます。学校に行くことができない子どもたちは、通常の授業や活動に参加することができず、学習や成績評価において不利になる可能性が高いからです。
学習を補ったり、小中学校の卒業に必要な出席日数を満たしたりするために、教育支援センター(適応指導教室)やフリースクール、別室登校などを利用することは可能です。しかし、これらの場所では、自習が中心となる場合や、学習を主な目的としていない場合も多く、学習機会の担保という面では十分とは言えないケースもあります。さらに、文部科学省委託の調査によると、自宅での学習を「よくしていた」と答えた児童生徒は約1割に留まっており、自宅で学習を進めることが簡単ではないことが分かります(※2)。
不登校の子どもたちは、将来的にひきこもりやニートになる可能性も高いと言われています。不登校によって子どもたちの将来の可能性が狭まらないよう、今後の支援や制度のあり方を考えていく必要があります。
生活リズムが崩れる
不登校になると、決まった時間に登校しなくなるため、生活リズムが崩れやすくなります。家で1日中ネットやゲームをしている場合も多く、生活リズムの乱れに影響を与えています。同調査によると、不登校児童生徒の保護者の約4割が、昼夜逆転など生活リズムが大きく乱れていたことが頻繁に、または時々あったと回答しています(※2)。
他者との関わりがなくなる
不登校になることで、他者との関わりが絶たれてしまうことも問題です。学校に行くことが難しい場合、教育支援センター(適応指導教室)やフリースクールを利用することも可能です。しかし、同調査ではこれらの場所に行っていないと回答した児童生徒がそれぞれ約9割に及んでおり、ほとんど自宅に留まっているケースが多いのが現状です(※2)。外出や家族以外の人との関わりを避けている場合も多く、不登校で他者との関わりが途絶えたことで、そのままひきこもりになるケースも見られます。
出典:(※2)文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究 報告書 | 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター

不登校への対策・支援
増え続ける不登校に対して、対策や支援の動きも広がっています。ここでは、不登校を防ぐための取り組みや、不登校の子どもたちが将来を切り開いていけるための支援についてご紹介します。
COCOLOプラン
2023年、文部科学省は、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」として「COCOLOプラン」を発表しました。このプランでは、不登校により学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることを目指し、社会全体で取り組むための方針をまとめています。
1.不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える
- 不登校特例校(学びの多様化学校)の設置を促進することで、不登校児童生徒の実態に配慮した教育を実現する。
- 校内教育支援センターの設置を促進し、自分のクラスに入りづらい児童生徒でも落ち着いて学習・生活ができる環境を整える。
- ICTの活用や民間施設との連携強化等により、教育支援センターの機能を強化する。
- 高等学校等においても柔軟で質の高い学びを保障する。
- クラス変更や転校等の柔軟な対応や、自宅学習の充実、民間施設や地域との連携等を通して、多様な学びの場、居場所を確保する。
2.心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する
- 1人1台端末を活用し、心や体調の変化の早期発見を促進する。
- 子どものSOSに対して、「チーム学校」により早期支援を推進する。(教師やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、養護教諭、学校医等の連携、こども家庭庁との連携等が求められる。)
- 保護者が一人で悩みを抱え込まないように、情報提供やコミュニティの強化等により支援する。
3.学校の風土の「見える化」を通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする
- 学校の風土を「見える化」し、学校運営の改善に役立てる。
- 子どもたち一人一人が前向きに学べるように、学校で過ごす時間の中で最も長い「授業」を改善する。
- いじめ等の問題行動に対しては毅然とした対応を徹底する。
- 児童生徒が主体的に参加した校則等の見直しを推進する。
- 「明日また行きたい学校」となるために、快適で温かみのある環境を整備する。
- 障害や国籍言語等の違いに関わらず、色々な個性や意見を認め合う共生社会を学ぶ場にする。
不登校の子どもたちへの遠隔教育の拡充
不登校の子どもたちに対する遠隔教育の整備も進められています。教室に入ることが難しい子どもたちに対して、自宅や教育支援センター等と教室を中継でつなぎ、教室にいなくとも授業に参加することを可能にするのです。静岡県静岡市では、別室登校している児童生徒に対し、別室と教室をつないだ実践が行われました。こうした取り組みは、子どもたちの学習支援だけではなく、学校の負担の軽減にもつながります。ICTを活用することで、個別の学習指導や教員による自宅訪問等を行う必要がなくなり、継続的な支援が可能になるのです。
出典:遠隔教育システム活用ガイドブック 第3版 | 文部科学省
不登校の子どもたちの学校以外の居場所
最後に、学校に通うことが難しい子どもたちにとって居場所となる場所を3つご紹介します。これら3つ以外の選択肢も考慮し、不登校の子どもたち一人一人が自分に合った選択をすることが大切です。
教育支援センター(適応指導教室)
教育支援センター(適応指導教室)は、教育委員会などが設置した施設で、集団生活への適応や、情緒の安定、基礎学力の補充、生活習慣の改善等を目指して、相談や指導を行っています。在籍している学校と連携を取りながら、個別カウンセリングや集団での指導、学習支援などが、組織的かつ計画的に行われています。現在は、ICT環境の整備や、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置が進められています。
「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果 | 文部科学省
不登校特例校(学びの多様化学校)
不登校特例校(学びの多様化学校)とは、文部科学大臣が指定し、不登校の子どもたちの実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校を指します。例えば、子どもたちの学習状況に合わせた少人数指導や習熟度別指導、家庭訪問や保護者への支援、学校外の学習プログラムの活用などの工夫をすることが目指されています。現在、COCOLOプランの下で、設置の拡充が進められています。
出典:学びの多様化学校の設置に向けて 手引き | 文部科学省
フリースクール
フリースクールと呼ばれる民間の施設を利用するという選択肢もあります。フリースクールには決められたカリキュラムがないため、施設の規模や教育理念、活動内容、利用費用等は様々であり、子どもたちの個性や主体性を重視した教育が行われています。
関連記事は下記からご覧ください。

不登校の現状:まとめ
不登校の子どもたちは年々増加しており、その背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。不登校が長期化すると、将来的にひきこもりにつながる可能性もあります。こうした状況に対し、文部科学省の「COCOLOプラン」や、教育支援センター、フリースクールの整備など、対策や支援の動きも進んでいます。
不登校は、決して特別なことではなく、誰にでも起こりうる身近な問題です。大切なのは、「不登校」という状況そのものにとらわれるのではなく、その子どもが抱えている不安や困りごとに寄り添い、安心して学び、成長できる環境を整えることです。私たち一人ひとりが「どの子どもも取り残さない」という意識を持ち、子どもたちの声にしっかり耳を傾けることが、不登校の解決に向けた第一歩となります。子どもたちが自分らしく未来を切り開いていけるように、社会全体で温かく見守り、支えていきましょう。
update: 2025.3.23