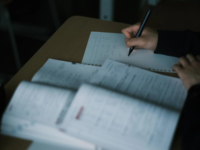フリースクールとは?気になる出席認定や選ぶポイントについても解説
update: 2025.3.9
フリースクールは、主に不登校の子どもたちが安心して学び、成長できる場所です。学校に行かなくても学習を続けたり、社会とつながる機会を得ることができます。この記事では、フリースクールの費用や出席認定の可否、様々なフリースクールのタイプや選ぶポイントなどについて、詳しく解説します。
Contents
フリースクールとは?気になる出席認定や選ぶポイントについても解説
フリースクールとは?
フリースクールとは、個人・NPO法人・任意団体等が運営する民間の教育機関です。主に不登校の子どもたちが利用しています。決められたカリキュラムがないため、規模や教育理念、活動内容、費用等は施設によって様々であり、子どもたちの個性や主体性を尊重した教育が行われています。
フリースクールは、学校に通いながら利用することも可能です。「週に2日だけ学校に通う」など、子どもの意欲や体調に合わせて利用することができます。
フリースクールに通う子どもたちの特徴
フリースクールには、小学生から高校生まで、幅広い年齢の子どもたちが通っています。年齢の違う子どもたちが一緒に活動しているため、年上の子どもが年下の子どもに教えたり、手助けをしたりといった様子が日常的に見られます。
フリースクールに通う背景は、人それぞれ異なります。例えば、学校でのいじめや、発達障害による困難、家庭の事情など、様々な要因が挙げられます。
また、フリースクールは民間の施設であるため、一般的な入学資格や条件は定められていません。ただし、施設によっては「小学生のみ」、「1人で通学できる場合のみ」といった制限が設けられている場合もあります。
フリースクールは出席認定はされる?
小中学生の場合、フリースクールの利用が学校の出席扱いになる可能性があります。これは、一定の要件を満たし、学校長の承認を得られた場合に限られます。出席扱いとして認められないこともあるため、注意が必要です。出席扱い制度を利用したい場合は、在籍している学校とフリースクールに事前に相談をすることが重要です。
フリースクールとサポート校や適応指導教室との違いは?
サポート校との違い
サポート校は、通信制高校に通う生徒の学習支援を主な目的とする民間の教育機関です。サポート校では、一般的に入学資格として「中学卒業見込み者」、「通信制高校在籍者」などが設けられています。
適応指導教室(教育支援センター)との違い
適応指導教室は、不登校の小中学生のための居場所の提供や復学を目的として各市町村の教育委員会により運営されています。主に、集団生活への適応や情緒の安定、基礎学力の補充などのサポートが行われています(※1)。フリースクールと比べ、学校の出席扱いとして認められやすい現状があります。一方で、カリキュラムに縛られないフリースクールでの活動が子どもたちに合っている場合もあるため、状況に応じた選択をすることが重要です。
出典:※1 適応指導教室(学校支援センター)の取り組みについて | 森敬之
参考:オルタナティブスクール
近年、オルタナティブスクールという選択肢も注目されています。オルタナティブスクールは、体験型学習などの革新的な教育方法により、子どもの可能性を伸ばすことを目的としています。フリースクールが「学校に行けない子どもたちのための居場所」という救済的な意味合いが強い一方で、オルタナティブスクールは、学習指導要領に基づいた従来の画一的な学校教育を疑問視する親や本人が積極的に利用しています。
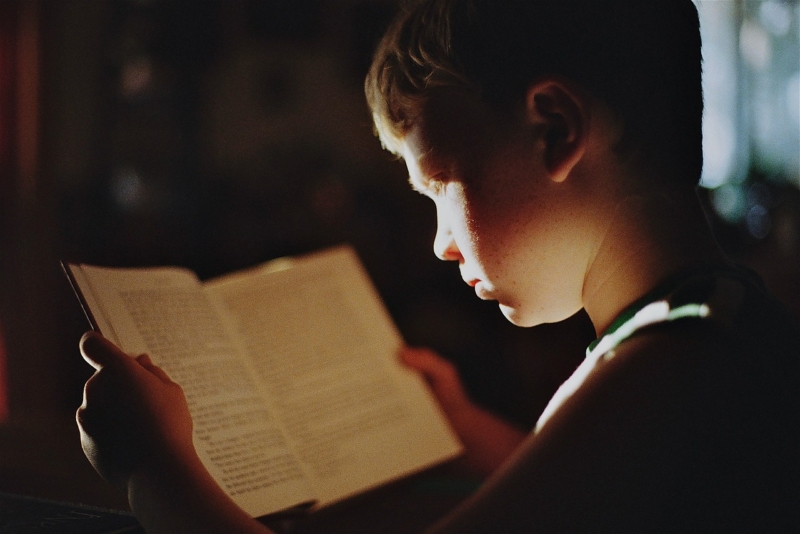
フリースクールの費用
フリースクールに通うには、費用がかかります。文部科学省の調査によると、入会金に1万円から3万円ほど、会費(授業料)に月額で1万円から5万円ほどかかる場合が多いと言われています(※2)。
出典:※2 小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査 | 文部科学省
フリースクールが増加している背景
フリースクールは、不登校児童生徒数の増加とともに2000年代から増え始めました。また、教育ニーズの多様化や、従来の学校教育では子どもたちの個性や能力に対応できないといった認識の広まりから、個々のニーズに合った柔軟な教育を実現するフリースクールの需要が高まっています。
フリースクールでの活動内容
フリースクールには共通の定められたカリキュラムが存在しないため、活動方針や教育形態、使う教材などは施設によって異なります。文部科学省の調査(※3)によると、個別の学習支援の実施率が最も高く、約85%の団体・施設で行われています。また、社会体験(職場体験など)や自然体験(農業体験など)、音楽や美術などの芸術活動やスポーツに関しても、それぞれ半分以上の団体・施設で実施されています。その他にも、宿泊体験や子どもたちによるミーティングなど、施設によって様々な活動が行われています。
独自の活動として、子どもの主体的な学びを重視したプロジェクトベースの学習や、IT関連や芸術分野などでのスキルの習得に特化した教育、資格取得の支援などを行っている所もあります。これらのフリースクールは、やりたいことや好きなことがはっきりしている子どもや、将来に役立つ資格を取得したい子どもに向いています。
出典:※3 民間の団体・施設との連携等に関する実態調査 | 文部科学省
フリースクールの目的・役割
続いて、フリースクールの目的や役割についてご紹介します。フリースクールを選ぶ際には、その目的や役割がその子どもに合った所を選ぶようにしましょう。
学校復帰を目指す
子どもの学校復帰を目的としているフリースクールでは、復帰後に学校の授業についていけるように、学校のカリキュラムや授業進度に合わせた学習指導が行われています。学校生活にスムーズに馴染めるように、学校と同様の時間割が組まれている所や、グループ活動を積極的に取り入れている所もあります。
卒業まじかの子どもに対しては、進路先を決めるためのサポートや受験に向けた学習支援を行っている場合もあります。
子どもたちの「居場所」となる
学校に行けない子どもたちの中には、学校での学習や人間関係が上手くいかず、自信を失くしている子どもや、将来に希望を持てない子どもがいます。そういった子どもたちに対して、「安心して過ごせる居場所」としてフリースクールが機能している場合もあります。この場合、子どもたちがスタッフや他の子どもたちと過ごす中で、徐々に学ぶ意欲や自信を取り戻し、気力を回復させることを最優先に目指しています。
社会とのつながりを持たせる
子どもが不登校になると、 他者と関わる機会が減ります。社会から取り残されたように感じ、さらに自分の殻に閉じこもるという悪循環に陥る場合もあります。 フリースクールは、不登校の子どもにとって家族以外の人と関われる貴重な場であり、社会とのつながりを保つ役割があります。 このようなつながりが、子どもの不安や心の負担を和らげてくれるでしょう。
学習のサポートを行う
学校に行けなくても勉強を頑張りたい子どもたちに対して、学習支援を重点的に行っているフリースクールもあります。苦手科目を重点的に学ぶことができたり、習熟度や希望に応じた学習サポートを受けることができたりします。施設によっては、専門の先生から学ぶことができる場合もあります。
専門的な支援を提供する
不登校になった子どもたちの中には、心身の病気や疾患を抱えている子どもたちもいます。そういった子どもたちへの医療的なケアや専門家のサポートを提供し、安心して通える場所を提供しているフリースクールもあります。例えば、発達障害や学習障害の子どもに対しては、困難に応じた学習支援や対人コミュニケーションのトレーニングを行うなど、個々の特性や状況に合わせたサポートが行われています。
親の安心にもつながる
自分の子どもが不登校になってしまった際に、子どもに「安心して過ごせる居場所」や適切なサポートがあることは、親の安心にもつながります。また、フリースクールは似たような状況にいる子ども同士や親同士の交流の場ともなります。情報交換や共感をし合える存在がいることは、親にとっての支えとなり、不登校の子どもを持つ家族全体の不安を和らげることにつながります。

フリースクールの形態
フリースクールには、様々な形態があります。ここでは、4つのタイプをご紹介します。
通学型
通常の学校と同様に、フリースクールに通学して活動を行うタイプです。通学型のフリースクールでは、スタッフや他の子どもたちと対面でリアルなコミュニケーションをとることができます。これは、社会性やコミュニケーション能力を育む上で重要です。
自宅訪問型
ひきこもり状態が長引き、外出へのハードルが高い、フリースクールに通うことも難しい場合
スタッフが自宅訪問 外出意欲を高めることが目的
子どもの安心できる場所に訪問し、遊び相手や話し相手になる 信頼関係を築き、外への興味を引き出す
勉強だけでなく、子どもが興味のあるゲームや運動などを一緒に何かをする時間を共有することで徐々に外出意欲を高める
オンライン型
オンライン上での交流や学習機会の提供、その他の支援を行うフリースクールも存在します。外出することに不安を抱える子どもでも、自宅に居ながら活動に参加することができます。近年は、メタバースなどを活用した革新的な指導法も実施されています。
共同生活型
共同生活型のフリースクールでは、子どもたちがスタッフや他の子どもたちと寮などで生活しながら、社会性や自立心を育む教育が行われています。学習に加え、掃除や食事などを分担して行っており、ルールを設けて適切な生活習慣を教え込むところや、自主性を重んじるところなど、施設によって特色があります。ひきこもりから抜け出したい子どもや、家庭環境が不安定で支援が必要な子ども、家事や生活力を身につけたい子どもが利用し、日々の生活で互いに協力し合う中で責任感や協調性を身につけることができます。
フリースクール卒業後の進路
フリースクール卒業後の進路は様々です。小中学生の場合、フリースクールでの活動が出席扱いとされていれば、中学校や高校への進学が可能となります。高校生の場合は、「高等学校卒業程度認定試験」に合格することで、大学進学をすることができます。その他にも、専門学校への進学や就職、留学などが挙げられます。進路を考える際には、子どもの意向や状態に応じた適切な選択をすることが大切です。フリースクールでは、進路相談や情報提供を実施している場合がほとんどであるため、一度相談してみましょう。
フリースクールを選ぶポイント
様々なタイプのフリースクールが存在する中で、どのフリースクールを選べばよいのでしょうか。ここからは、フリースクールを選ぶ際のポイントについて5つご説明します。
フリースクールの環境が子どもに合っているか
フリースクールのサポート体制や雰囲気は様々です。その中で、子どもが「通いたい」と思い得るか、リラックスして過ごせるかが最も重要なポイント。不登校の子どもたちの困難や特性に合ったフリースクールを選ばなければ、続かない可能性が高く、むしろ悪影響となる可能性もあるため、注意が必要
施設の見学やスタッフへの相談を通して、実際にフリースクールごとの雰囲気を感じ、判断すると良いでしょう。
フリースクールに通学しやすいかどうか
通学型のフリースクールの場合、通学のしやすさが重要なポイントとなります。子どもにとって通学自体が負担になると、行かなくなってしまう可能性があるからです。通学時間や、利用する交通機関の込み具合といった通学路の環境が子どもにとって問題がないか、事前に確かめましょう。
費用がどのくらいかかるか
フリースクールに通うには、入会金や授業料がかかります。自治体によってはフリースクールの利用にかかる費用の補助を受けられる場合もあるため、利用できる補助金制度があるかどうか確かめておきましょう。また、交通費がどのくらいかかるかも、考慮する必要があります。
フリースクールの運営元が信頼できるか
フリースクールを開業するには特別な資格や審査は必要ないため、ずさんな運営を行っている施設がある可能性もあります。そのため、フリースクールの運営元が信頼できるかどうかは事前に確認しておく必要があります。運営元が別事業での実績のある企業であったり、WEBサイトなどで活動の様子を公開している場合は、信頼できる可能性が高いといえます。
出席認定制度を利用できるかどうか
小中学生の子どもの場合、フリースクールでの活動が「出席扱い」として認められるかは施設によって異なるため、確認しておきましょう。出席認定制度を利用することで、学校への復帰や進学、就職に備えることができます。
フリースクール以外の「居場所」
子どもの居場所は、小中学校やフリースクールだけではありません。適応指導教室(教育支援センター)や不登校特例校、夜間中学、通信制高校、塾や習い事、アルバイト、地域のコミュニティなど、様々な選択肢があります。これらの選択肢を考慮し、悩みや特性に応じて最適な場所を選択することが大切です。

フリースクールは?まとめ
フリースクールは、不登校の子どもたちにとって大切な学びと居場所の選択肢の一つです。学校復帰を目指すものや、自由な学びを重視するものなど、施設によって特徴が異なります。その他にも、出席認定の有無や費用、通学のしやすさなどを考慮し、子どもに合った施設を選ぶことが大切です。適応指導教室や通信制高校など、他の選択肢とも比較しながら検討しましょう。
update: 2025.3.9